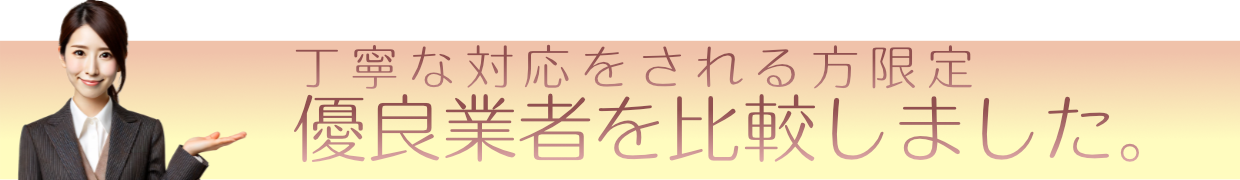更新日:2025年2月27日 | Tatsumi
墓じまいを考える方が増えています。お墓を守ることは大切なことですが、維持費や管理の負担が重くのしかかる場合もあります。現代では、家族構成や価値観の変化により、墓じまいを選択する人が増加しています。
この手続きは、親族との相談、必要な書類の準備、墓石の撤去工事など、慎重に進めることが求められます。本記事では、墓じまいの具体的な手順や注意点、必要書類について分かりやすく説明します。家族や先祖への感謝を大切にしながら、安心して進めるための知識をお伝えします。

一方で、悪い点としては、手続きが複雑で時間や手間がかかることや、親族間で意見が分かれる場合があることが挙げられます。また、菩提寺とのやり取りや離檀料の発生、石材店の選定など、費用や対応に慎重さが求められる場面が多いです。さらに、遺骨の新しい供養先を選ぶ際にも慎重な検討が必要です。
墓じまいには、メリットとデメリットの両面がありますが、大切なのは家族や先祖を大事に思う気持ちを忘れず、自分たちにとって最適な方法を見つけることです。感謝を込めた選択ができるよう、適切な準備と相談を進めることが大切です。
墓じまいが増える理由

現代社会で、墓じまいを考える人が増えています。その背景を理解することで、自分や家族にとって最適な選択を見つける助けになります。
社会や家族の形が変わった影響
少子高齢化や核家族化が進む日本では、家族の形が変わりつつあります。地方の過疎化も影響し、お墓を維持する人が減っています。これらの変化により、遠方に住む人や子孫がいない家庭では、お墓の管理が難しくなり、墓じまいを選ぶケースが増えています。こうした背景を理解し、最適な選択を考えることが大切です。
- 地方では人口減少が進み、地域社会の力が弱まっています。
- 子どもが少なくなり、お墓を引き継ぐ人がいない家庭が増えています。
- 親族が遠くに住んでいて、お墓の管理が難しい状況があります。
- 過疎化が進む地域では、共同でお墓を守ることが難しくなっています。
ポイント: 家族構成や地域の変化が、墓じまいを選ぶ背景になっています。
人々の考え方が多様化していること
個性や自由を大切にする現代では、お墓に対する考え方も変わっています。これまでのように「家族全体で守る」スタイルだけでなく、個人の希望やライフスタイルに合わせた供養の方法を選ぶ人が増えています。新しい価値観が広がり、選択肢が増えているのが特徴です。
- 「家族単位でのお墓管理」から個人の希望を優先する傾向があります。
- 自然葬や樹木葬など、新しい供養方法が注目されています。
- 人々の価値観が多様化し、自由な選択肢を求める声が増えています。
- 従来の形式に縛られない、柔軟な供養を選ぶ人が増加しています。
ポイント: 現代では、家族単位から個人の価値観に合わせた供養が重視されています。
無縁墓の問題が注目されている背景
無縁墓とは、管理する人がいなくなったお墓のことです。この問題は、近年社会問題として注目されています。ニュースやメディアで取り上げられることが増え、多くの人が自分のお墓の将来を考えるきっかけになっています。無縁墓を避けるために、墓じまいを選ぶ人も増加しています。
- 無縁墓が増え、地域や墓地の維持に支障が出ています。
- メディアが問題を取り上げ、認識の高まりにつながっています。
- 家族が管理できない場合に備え、早めの対応が求められています。
- 遺骨を他の形で供養する選択が、無縁墓回避の手段となっています。
ポイント: 無縁墓の問題が社会的に認識され、墓じまいを考える動機となっています。
経済的な負担を減らしたい人が増えている
お墓の維持には管理費などの継続的な費用がかかります。この負担を減らすため、永代供養などの新しい選択肢を選ぶ家庭が増えています。次世代に負担を残さないため、墓じまいを選択する動きが広がっています。これは単なる遺骨の移動ではなく、社会の変化や個々の価値観が反映された選択と言えます。
- 管理費が家計に負担をかけるケースがあります。
- 永代供養や樹木葬など、代替手段が注目されています。
- 次世代に負担を残したくないという理由で墓じまいを選ぶ人が増えています。
- 経済的理由が、墓じまいを考える大きな動機の一つです。
ポイント: 墓じまいは、経済的負担を軽減しつつ新しい供養方法を選ぶ現代の傾向を反映しています。
墓じまいを進める手順
墓じまいには、いくつかのステップがあります。それぞれを正確に進めることで、スムーズな手続きが可能になります。
家族や親族と話し合いをする
墓じまいを考える際は、まず親族と相談することが大切です。費用がかかるため、独断で進めると親族間のトラブルにつながる場合があります。また、お墓を管理し続けたいと考える人もいるかもしれません。さらに、墓じまいをすることでお墓参りの場がなくなり、親族のつながりを損なう可能性もあります。しっかりと話し合い、全員の了承を得ることで円滑に進めることができます。
- 墓じまいを進める前に、全員の意見を聞くことが必要です。
- お墓を続けたいと考える親族の気持ちを尊重してください。
- 高額な費用が発生するため、トラブルを防ぐ話し合いが重要です。
- お墓参りがなくなる影響を考慮することも大切です。
ポイント: 親族全員で話し合い、納得を得ることが墓じまいを円滑に進める基本です。
墓地の管理者やお寺と相談する
墓地管理者やお寺への相談は、墓じまいを進める上で欠かせません。管理者の了承が得られなければ、手続きが進まないため、早めに連絡して状況を伝えることが大切です。特に、檀家の場合は離断の手続きが必要となり、お寺の運営にも影響を与える可能性があります。これまでお世話になった感謝を伝え、円満な関係を保つことが大切です。
- 管理者やお寺の了承がなければ、墓じまいの手続きは進められません。
- 檀家を離れる場合は、お寺の運営にも影響があることを理解してください。
- 感謝の気持ちを伝え、事前にしっかり相談することが重要です。
- 丁寧な対応がトラブルを防ぎ、良好な関係を続けるきっかけになります。
ポイント: 墓じまいを進めるためには、管理者やお寺と誠実に相談することが必要です。
新しい供養の方法や遺骨の受け入れ先を探す
新しい供養先を選ぶことは、墓じまいの大切なステップです。親族や管理者への相談を終えた後、適切な場所を検討します。霊園や納骨堂には空き状況に変動があるため、候補を早めに絞ることが重要です。お墓の種類や費用を具体的に調べておくことで、スムーズに選べます。また、一部の地域では、新しい供養先が決まっていないと手続きが進まない場合があるため、早めの準備を心がけてください。
- 空き状況が変わるため、候補を早めに調査することが必要です。
- 納骨堂や樹木葬など、供養方法の選択肢を比較してください。
- 地域によっては、新しいお墓の決定が手続きの条件となる場合があります。
- お墓の種類や費用を調べて、具体的な計画を立てることが大切です。
ポイント: 早めに候補を絞り、費用や条件を確認した上で新しい供養先を決めましょう。
墓石の解体を依頼する石材店を決める
墓石の解体や撤去は、専門の石材店に依頼します。地域によっては、手続き書類に石材店の情報を記載する必要がある場合もあるため、事前に適切な業者を選んでおくことが大切です。また、撤去費用が高額になることもあるため、複数の石材店から見積もりを取り、比較することで費用を把握できます。さらに、管理者が指定する石材店しか利用できない場合もあるため、事前に確認をしておきましょう。
- 手続きには石材店の情報を記載する場合があるため、早めの選定が必要です。
- 複数の石材店に見積もりを依頼して、費用を比較してください。
- 撤去費用が高額になることがあるため、納得できる金額で依頼しましょう。
- 石材店が施設で指定されている場合があるため、管理者に確認が必要です。
ポイント: 見積もりを比較し、管理者の条件も考慮して適切な石材店を選びましょう。
行政手続きで必要な準備を進める
墓じまいを進めるためには、自治体での法的手続きが必要です。現在のお墓を引っ越しする許可を得るため、「改葬許可証」を発行してもらう手続きを行います。この許可証がなければ、遺骨を移動することはできません。まず、お墓を管轄する自治体の窓口で「改葬許可申請書」を受け取り、必要事項を記入して提出します。手続きを進める前に、申請書に必要な書類を確認しておくとスムーズです。
- 「改葬許可証」は遺骨を移動する際に必要な証明書です。
- 管轄の自治体窓口で「改葬許可申請書」を入手してください。
- 申請には、必要書類の提出が求められるため、事前に準備を進めましょう。
- 法的な手続きを怠ると、墓じまいが進められなくなる場合があります。
ポイント: 自治体での手続きは、改葬許可証を取得するための重要なステップです。事前準備を整えて進めましょう。
閉眼供養を行い遺骨を取り出す
閉眼供養は、仏式で墓じまいを行う際に行う大切な儀式です。この供養には、お墓に眠る故人や先祖の魂を通常の状態に戻すという意味があります。「お性根抜き」や「魂抜き」とも呼ばれるこの儀式では、僧侶が読経を行い、魂を静かに送り出します。
菩提寺がある場合は、そちらに依頼するのが一般的ですが、ない場合でも近隣のお寺に相談して手配することが可能です。閉眼供養は墓石の解体工事と同じ日に行う必要はなく、1週間ほど前に済ませることもできます。事前にスケジュールを調整しておくとスムーズです。
- 閉眼供養は、魂を通常の状態に戻すための仏式の儀式です。
- 菩提寺があれば依頼し、ない場合は近くのお寺に相談してください。
- 僧侶による読経を行い、故人や先祖を敬いながら儀式を進めます。
- 解体工事の当日ではなく、事前に行うことも可能です。
ポイント: 閉眼供養は、墓じまいの中で最も敬意を払うべき重要な儀式です。事前準備をしっかり整えましょう。
墓石を解体・撤去してもらう
墓石の解体・撤去は、墓じまいの重要な工程の一つです。作業中に確認したい場合は、現場に立ち会うことも可能です。解体費用は地域や石材店によって異なりますが、一般的なお墓の場合、10万円前後が相場とされています。
墓石を撤去した後は、土地を更地にして返還する必要があります。そのため、慎重に業者を選び、作業内容や費用について納得した上で依頼することが大切です。解体工事の日程や費用の詳細については、石材店との事前の打ち合わせをしっかり行いましょう。
- 墓石の解体費用は地域や業者によって異なり、相場は10万円前後です。
- 解体後の土地は更地にして返還する必要があります。
- 作業の進行を確認したい場合は、現場に立ち会うことが可能です。
- 業者選びは慎重に行い、契約前に見積もりを確認してください。
ポイント: 墓石の解体・撤去は、費用や作業内容を確認しながら慎重に進めることが重要です。
墓地を元の状態に戻し返還する
墓石の解体作業が終わった後、墓地を更地にして元の管理者へ返還します。この際、不完全な状態で返還すると後でトラブルになる可能性があります。作業完了後に現場をしっかり確認し、契約内容に沿って返還を進めることが大切です。返還手続きは、墓地の契約書や管理者の指示に従い、慎重に行いましょう。
- 墓地は更地にする必要があります。
- 作業完了後、不備がないか現場をよく確認してください。
- 管理者への返還手続きは契約内容を守って進めることが大事です。
- 不完全な返還は、後々のトラブルの原因になる場合があります。
ポイント: 墓地を更地にした後、管理者への返還手続きは正確に進めましょう。
遺骨を新しい場所で供養する
墓じまいを終えた遺骨は、新しい改葬先に納めます。遺骨を移動する際は、丁寧に取り扱うことが大切です。自分の車やタクシーを使う場合は、骨壷が壊れないようしっかり固定してください。公共交通機関を利用する際は、他の乗客への配慮を忘れずに行いましょう。専用のバッグやケースを使用することで、安全に運ぶことができます。また、飛行機での移動時には、各航空会社の規定に従い、必要な準備をしておくことが重要です。
- 遺骨を運ぶ際、骨壷が壊れないよう固定してください。
- 公共交通機関を使う場合は、他の乗客に配慮しながら運びます。
- 専用のバッグやケースがあると、移動がより安全になります。
- 飛行機を利用する際は、航空会社のルールを事前に確認してください。
ポイント: 遺骨は丁寧に運び、新しい改葬先で適切に供養を進めましょう。
必要な書類と手続きの流れ

墓じまいには複数の書類が必要です。正確に準備することで手続きをスムーズに進められます。
改葬許可申請書を準備する
お墓を撤去する際には、自治体の許可を得る必要があります。勝手に遺骨を取り出すことは認められていないため、手続きをしっかり行いましょう。まず、「改葬許可申請書」を用意し、必要事項を記入して現在のお墓がある市区町村役場に提出します。遺骨1体ごとに1通が必要です。自治体によっては、申請書をホームページからダウンロードできる場合もあります。
- 改葬許可申請書を準備し、必要事項を正確に記入してください。
- 遺骨1体につき1通が必要であるため、数を確認しておきましょう。
- 自治体のホームページから申請書をダウンロードできる場合があります。
- 許可を得ずに遺骨を取り出すことは認められていませんので注意が必要です。
ポイント: 改葬許可申請書は、自治体での手続きに必須の書類です。正確に準備し、提出を進めましょう。
埋葬証明書を用意する
遺骨を埋葬している証明は、改葬許可申請を進める際に必要です。「改葬許可申請書」に墓地管理者の署名と捺印が求められます。郵送で手続きができる場合もあるため、事前に管理者に確認してください。また、自治体によって手続きが異なり、証明書(埋蔵証明書)の提出が求められるケースもあります。自治体の指示に従い、必要な書類を正確に用意しましょう。
- 「改葬許可申請書」には、墓地管理者の署名と捺印が必要です。
- 管理者が郵送対応可能か、事前に確認してください。
- 一部自治体では、「埋蔵証明書」の提出が求められることがあります。
- 自治体ごとに異なる手続きの流れを確認し、正確に対応してください。
ポイント: 埋葬証明は手続きに必要な書類です。自治体や管理者に確認しながら進めることが重要です。
墓地の名義人の承諾書を用意する
墓地の名義人が改葬許可申請者と異なる場合、「承諾書」の提出が必要です。この書類には名義人の署名と捺印が求められます。承諾書の様式は、墓地を管轄する自治体から取り寄せる必要があります。自治体のホームページで様式がダウンロードできる場合もあるため、事前に確認すると手続きがスムーズになります。
- 名義人と申請者が異なる場合、承諾書が必要です。
- 名義人の署名と捺印を事前に用意してください。
- 承諾書の様式は、管轄の自治体から取り寄せてください。
- 一部自治体では、様式がホームページで入手可能です。
ポイント: 名義人が異なる場合は、承諾書を正確に準備し、提出しましょう。
遺骨の受け入れ証明書を準備する
自治体によっては、「受け入れ証明書」の提出が求められます。この書類は、新しい改葬先で遺骨を受け入れることを証明するものです。改葬先の管理者に名前や住所を記入し、捺印をしてもらいます。また、自治体によっては、「墓地使用許可証」などの写しを提出することで受け入れ証明書が不要になる場合もあります。事前に詳細を自治体に確認して、手続きを進めましょう。
- 受け入れ証明書は、新しい改葬先での遺骨の受け入れを証明する書類です。
- 管理者に記入と捺印を依頼してください。
- 「墓地使用許可証」の写しで代用できる場合もあります。
- 詳細は各自治体の規定を確認することが大切です。
ポイント: 新しい改葬先の受け入れ証明を正確に準備することで、手続きがスムーズに進みます。
書類を役場に提出して手続きを行う
改葬許可申請に必要な書類一式(改葬許可申請書、承諾書、受け入れ証明書など)が揃ったら、役場の窓口に提出します。自治体によっては、認印や追加書類が必要な場合があります。そのため、申請前に自治体のホームページや窓口で確認することが重要です。提出時に不備があると手続きが遅れるため、しっかりと準備して申請に臨みましょう。
- 必要な書類(改葬許可申請書、承諾書、受け入れ証明書)を役場に提出してください。
- 自治体によっては認印やその他の書類が求められる場合があります。
- 必ず事前に自治体のホームページや窓口で詳細を確認しましょう。
- 提出時の書類不備を防ぐために、内容を再確認することが大切です。
ポイント: 必要書類をしっかり揃え、自治体の規定に従って役場に提出しましょう。
墓じまいを行う際の注意点
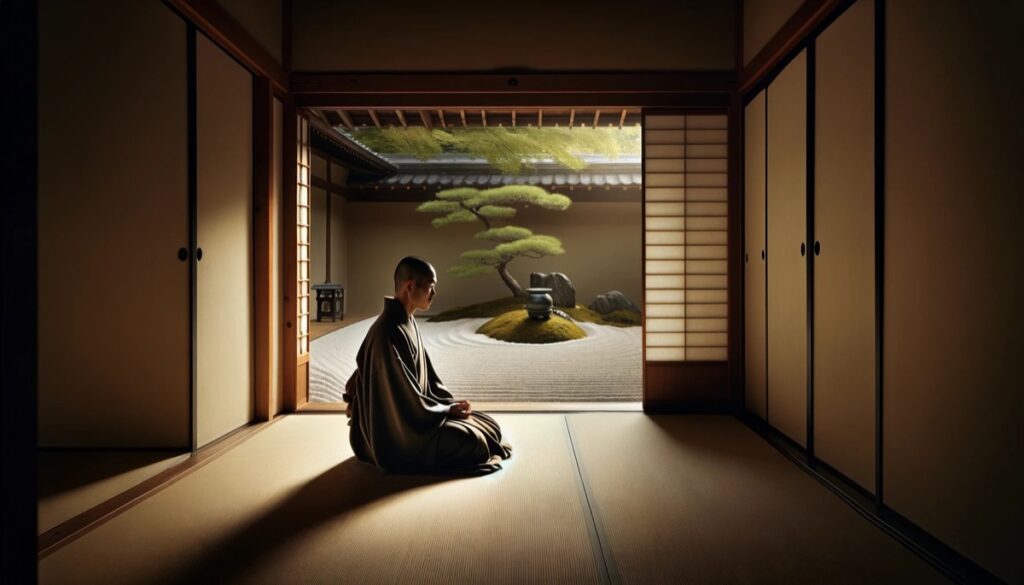
手続きの際にはいくつかの注意点があります。これを理解しておくことで、無駄やトラブルを防ぐことができます。
改葬許可申請書は自分で記入すること
改葬許可申請書は、申請者本人が記入する必要があります。代理申請をする場合でも、この書類の記載は本人でなければなりません。複数の遺骨を改葬する際は、1体につき1枚が必要です。ただし、一部自治体では1枚の申請書で複数分を記載できる場合もあるため、手続きを始める前に確認しておくと安心です。書類には早めに目を通し、必要な準備を整えましょう。
- 改葬許可申請書は本人が記入する必要があります。
- 委任状があれば代理申請が可能ですが、申請書自体は本人の記載が必須です。
- 複数の遺骨の場合、1体につき1枚の申請書が必要です。
- 一部自治体では1枚の申請書で複数の遺骨を記載できる場合があります。
- 早めに書類に目を通して、スムーズに準備を進めましょう。
ポイント: 改葬許可申請書は本人が記入し、必要書類を確認してから手続きを進めましょう。
墓石撤去前に手続きを終わらせること
墓石の撤去工事前に、改葬に必要な行政手続きを完了しておくことが大切です。手続きが終わっていない場合、工事が完了していても遺骨を新しい改葬先に移すことができません。遅くとも工事の1ヶ月前には、自治体を訪問したり、必要な書類を準備しておくことをおすすめします。早めに対応することで、墓じまいの流れをスムーズに進めることができます。
- 工事前に改葬手続きを完了させておく必要があります。
- 改葬先が未定では、手続きが進まないため注意が必要です。
- 遅くとも工事の1ヶ月前から手続きを始めましょう。
- 自治体の窓口を訪れるか、申請書類をホームページで取り寄せて準備してください。
- 早めの行動が墓じまいを円滑に進めるポイントです。
ポイント: 墓石撤去工事前には、必要な手続きを早めに済ませることが重要です。
墓石撤去の費用について事前に確認する
墓石の撤去費用は墓石の大きさや墓地の条件によって異なり、高額な請求がトラブルになることもあります。工事後に予想外の費用を請求されないために、石材店を選ぶ際は複数の見積もりを取ることが重要です。事前に費用を確認しておけば、急な請求に驚くことなく安心して依頼できます。見積もり内容を比較し、納得できる業者を選びましょう。
- 費用は墓石の大きさや作業条件で変わります。
- 複数の石材店から見積もりを取ることでトラブルを防げます。
- 事前に費用を把握し、急な請求に備えられます。
- 費用や作業内容をしっかり確認し、信頼できる業者を選んでください。
ポイント: 複数の見積もりを比較し、費用や条件に納得した上で依頼しましょう。
菩提寺への礼儀を忘れずに対応する
現在のお墓が菩提寺に属している場合、墓じまいを進めるには離檀料を支払うケースがあります。離檀料は、これまでの感謝の気持ちを示すものとして贈与されるもので、相場は1万~20万円程度が一般的です。ただし、明確な決まりはなく、遺族が金額を決めることが基本とされています。中には高額な請求をされることもあるため、事前に礼を尽くして相談し、円満に理解を得ることが大切です。
- 離檀料は感謝の気持ちとして支払う費用です。
- 金額は1万~20万円程度が相場ですが、明確な基準はありません。
- 高額な請求を防ぐため、事前に菩提寺と丁寧に相談してください。
- 礼を尽くすことで、今後の関係を円満に保つことができます。
ポイント: 菩提寺には感謝を示し、誠実な相談を通じて理解を得ることが重要です。
問題が起きたら専門家に相談すること
墓じまいでトラブルが起きた場合は、早めに専門家に相談することが大切です。お寺の総括者や専門の弁護士に依頼することで、適切な解決策を見つけられる場合があります。また、国民生活センターも相談先の一つです。一人で悩まず、専門家の力を借りて問題をスムーズに解決することが安心につながります。
- お寺の総括者や専門弁護士に相談してください。
- 国民生活センターはトラブル相談窓口として利用できます。
- 一人で抱え込まず、信頼できる専門家にサポートを依頼しましょう。
- 早めの相談が、解決をスムーズに進めるための大切なステップです。
ポイント: トラブルが発生した場合は専門家を頼り、早めに適切な解決策を見つけましょう。
Auto Amazon Links: プロダクトが見つかりません。
まとめ:墓じまいのやり方手順と必要書類と手続きと注意点。なぜ墓じまいが増加している?
墓じまいは、先祖を敬う気持ちを大切にしながら、現代の生活環境に合わせた選択をする重要な手続きです。経済的負担や家族構造の変化により、多くの方が墓じまいを考えるようになっています。しかし、感情面や手続きの複雑さから悩む方も少なくありません。正しい知識と準備があれば、安心して進められます。
まず、墓じまいを始める前に親族全員と相談し、全員の同意を得ることが必要です。お墓は家族の共有財産であり、一人の判断で進めるとトラブルになる場合があります。その後、現在のお墓を管理する菩提寺や墓地管理者に相談し、理解を得ることが大切です。場合によっては離檀料が発生することもあるため、感謝の気持ちを伝えながら、丁寧に対応しましょう。
手続きには、「改葬許可申請書」や「埋葬証明書」などの必要書類を自治体に提出する必要があります。これらの書類が揃わなければ、遺骨を移動することができません。また、新しい供養先を早めに決めることも重要です。候補が決まらないと手続きが滞る可能性があるため、納骨堂や樹木葬など自分や家族に合った供養方法を調査し、適切な場所を選びましょう。
墓石の解体や撤去工事では、複数の石材店から見積もりを取り、費用や条件を比較することが大切です。費用が不明瞭なまま依頼を進めると、高額な請求につながることがあります。解体後、墓地を更地にして返還する際には、管理者と確認しながら進めると安心です。
最後に、墓じまいが完了したら、新しい供養先で遺骨を丁寧に供養します。移動時は骨壷の取り扱いに注意し、必要に応じて専用のバッグを使うと安全です。また、手続きや対応で困った場合は、専門家に相談することでスムーズな解決が期待できます。
墓じまいは、感謝の気持ちを持ちつつ、慎重に進めることで家族や先祖とのつながりを大切に保ちながら、新しい供養の形を実現するための大切なプロセスです。


私は墓の管理と墓じまいの専門家であり、10年を超える長きにわたり、墓の管理に困っている多くの家族に墓じまいの提案とサポートを行ってきました。
特に公営の墓地での一定期間の放置による墓の撤去や、墓の管理の困難さ、維持費の問題など、多くの家族が墓じまいを検討する理由はさまざまです。墓じまいの過程で必要となる墓地の管理者との相談や新しい供養の場所の選定など、これまでの経験を踏まえ、サポートするという視点で、墓の管理に困っている人を助けることができたらと感じています。