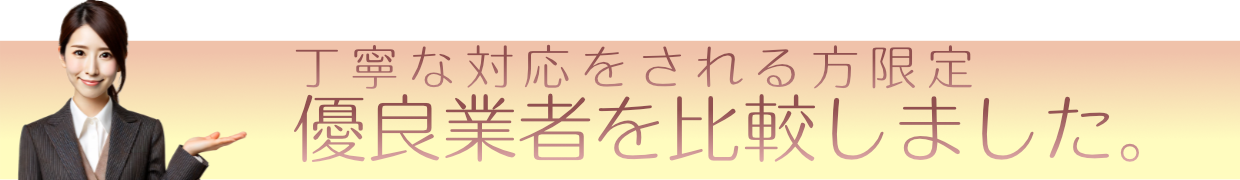更新日:2025年2月27日 | Tatsumi
墓じまいを考えている方にとって、先祖を敬う気持ちと現実の負担との間で悩むことが多いでしょう。お墓を守ることが難しくなったと感じたとき、自分で墓じまいを進めるための準備と手続きが重要です。
親族や墓地管理者との相談、必要な書類の準備、そして注意すべきポイントなど、順を追って進めることで、心の負担を少しでも軽くできます。この記事では、10年以上の経験を持つ専門家の視点から、墓じまいを円滑に進めるための具体的な方法をお伝えします。

しかし、一方で、手続きや書類の準備には時間と労力がかかり、特に初めての方にとっては複雑に感じることもあります。さらに、親族やお寺との相談がうまくいかない場合、心の負担が増すこともあります。墓じまいは大切な決断であり、その過程で感じる不安や葛藤も自然なことです。無理をせず、必要なときにはサポートを受けながら、丁寧に進めていくことが大切です。
墓じまいを始める前に準備すること

墓じまいを検討する際には、事前の準備が非常に大切です。墓じまいは、先祖を敬う心を持ちながらも、現代のライフスタイルや負担を考慮することが求められます。このセクションでは、墓じまいをスムーズに進めるための最初のステップをご紹介します。
親族との相談と合意形成を行う
墓じまいを考えるときには、事前に親族としっかり話し合い、理解を得ることが大切です。特に、遠くに住んでいる親族にも忘れずに相談し、全員で納得できる形を目指しましょう。
- 親族全員の理解を得ることが大事です。
- 遠方に住んでいる親族とも必ず相談します。
- 感情的な問題が絡むため、冷静に対話を行います。
- 相談を怠らず、全員で納得できる形にします。
親族とよく話し合い、全員が納得することがスムーズな墓じまいにつながります。
墓地管理者や菩提寺への確認と同意を得る
墓じまいには、現在の墓地管理者や菩提寺の理解が不可欠です。特に、特別な供養が必要になるため、早めに相談し、しっかりと話を進めることが大切です。
- 菩提寺には早めに相談しておくと安心です。
- 墓地管理者の理解を得ることが必要です。
- 魂を抜く特別な供養が必要です。
- 相談を早めに始めておくとスムーズです。
墓じまいは、墓地管理者や菩提寺の協力が必要ですので、早めに相談を開始しましょう。
遺骨の新たな供養方法や安置場所を決定する
墓じまい後の遺骨をどのように供養するか、事前に決めておくことが大切です。永代供養墓や納骨堂、樹木葬、散骨など、いくつかの選択肢があります。また、長年保管していた遺骨にはカビが生えている場合もあるため、お手入れを考慮して供養方法を決めましょう。
- 遺骨の新しい供養方法を早めに決めます。
- 永代供養墓や納骨堂など、選択肢を検討します。
- 長年保管していた遺骨はカビが生えることがあります。
- 遺骨のお手入れも含めて考えます。
遺骨の新しい供養方法を決めることが、墓じまい後の安心につながります。
墓じまいを進める具体的な手順
墓じまいを自分で進める際には、正しい手順を知っておくことが大切です。ここでは、具体的なステップを紹介し、スムーズに墓じまいを完了するための方法をわかりやすく説明します。一つ一つの手順をしっかりと踏むことで、後悔のない墓じまいができます。
親族と話し合う
墓じまいを進める前に、必ず親族に相談し、全員の了承を得ることが大切です。独断で進めると、後々のトラブルにつながることがあります。また、親族によってはお墓を守り続けたいという意見もあるため、慎重に話し合いましょう。
- 墓じまいには高額な費用がかかります。
- 親族の了承を得て、トラブルを避けます。
- 親族全員が納得できる形を目指します。
- お墓を守り続けたい親族もいる可能性があります。
親族との話し合いをしっかり行い、全員が納得する形で墓じまいを進めましょう。
墓地管理者やお寺と協議する
墓じまいを進めるには、墓地の管理者やお寺に事前に相談し、了承を得ることが不可欠です。特に、自分が檀家の場合、お寺との関係に影響が出るため、しっかりと話し合いをしておきましょう。
- 墓じまいには管理者の了承が必要です。
- 檀家の場合、お寺との関係に注意が必要です。
- 管理者への相談を忘れずに行います。
- お寺との関係を円満に保つため、事前に伝えます。
墓じまいをスムーズに進めるためには、管理者やお寺との事前の相談が大切です。
遺骨の供養方法と安置場所を決める
親族や墓地管理者への相談が済んだら、新しい供養方法や受け入れ先を決めることが重要です。霊園の空き状況や費用を事前に確認し、候補を絞っておくと、スムーズに進められます。地域によっては、新しい供養先の決定が手続きの条件になる場合もあるので、注意が必要です。
- 新しい供養先を早めに決めておきます。
- 費用やお墓の種類を具体的に考えます。
- 霊園の空き状況を確認しておきます。
- 地域によっては供養先の決定が条件です。
新しい供養方法や受け入れ先を早めに決定し、安心して手続きを進めましょう。
墓石の解体・撤去を依頼する石材店を選ぶ
墓石の解体や撤去を依頼する石材店を早めに決めておきましょう。費用が高額になることもあるため、見積もりを依頼し、複数の業者を比較すると良いです。管理者に確認して、指定の業者がある場合はそれに従う必要があります。
- 石材店は事前に選び、見積もりを取りましょう。
- 費用が高額になる場合があります。
- 申請書に石材店の情報を記入することがあります。
- 施設によっては指定の石材店があります。
石材店を選ぶ際は、費用や信頼性をしっかり確認してから契約しましょう。
墓じまいに必要な行政手続きを進める
墓じまいには、いくつかの行政手続きが必要です。これらの手続きを適切に進めることで、法律的な問題を避け、スムーズに進行できます。このセクションでは、具体的な書類や手続きの流れを詳しく説明します。正しい手続きを踏むことで、トラブルを防ぎ、安心して進められます。
改葬許可申請書を役所で取得する
改葬の手続きには、必ず「改葬許可申請書」を役所から入手する必要があります。この書類は、遺骨を新しい場所に移す際に役所へ提出する重要な書類です。申請書は各自治体によって異なりますが、遺骨や申請者の情報、改葬の理由などを記入します。申請書は、お墓のある市区町村の役所で受け取るか、自治体のホームページからダウンロードできます。
- 申請書は、お墓のある市区町村の役所で入手できます。
- 自治体のホームページからダウンロードも可能です。
- 記入する項目には、遺骨の本籍、氏名、申請者との続柄、改葬の理由などがあります。
- 発行費用は無料から500円程度です。
改葬許可申請書は、遺骨の移動をスムーズに進めるための重要な書類です。早めに入手し、必要な情報を正確に記入しましょう。
新しい安置場所の受入証明書を取得する
「受入証明書」は、遺骨を新しい墓地や霊園で受け入れることを証明する書類です。この書類は、役所が改葬許可を出すために必要です。新しい墓地や霊園の管理事務所で発行してもらい、申請者の情報や遺骨に関する情報を記載します。証明書の様式は市区町村によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
- 受入証明書は、新しい墓地や霊園の管理事務所で発行されます。
- 自治体のホームページからダウンロードできる場合もあります。
- 記入項目には、申請者の住所・氏名・電話番号や遺骨の情報が含まれます。
- 発行費用は無料から1,500円程度です。
- 墓地契約書の写しが確認資料になる場合もあります。
受入証明書を準備することで、改葬許可をスムーズに取得できるようになります。事前に必要な情報を確認し、適切に手続きを進めましょう。
埋葬許可証を取得する
埋葬許可証は、遺骨が現在のお墓に埋葬されていることを証明する重要な書類です。改葬手続きを進める際に必要となり、現在の霊園や墓地の管理人に発行してもらいます。民営墓地や公営墓地、寺院墓地によって入手場所が異なるため、事前に確認しておきましょう。
- 埋葬許可証は、現在の霊園や墓地の管理事務所や寺院で発行されます。
- 記入項目には、遺族の住所・氏名、管理者の署名・捺印、遺骨の情報が含まれます。
- 発行費用は無料から1,500円程度です。
- 改葬の理由や改葬先の情報も記入します。
埋葬許可証は改葬手続きに必須の書類です。適切な場所で早めに発行してもらい、手続きをスムーズに進めましょう。
改葬承諾書を取得する(該当する場合)
「改葬承諾書」は、墓地の使用者と改葬申請者が異なる場合に必要な承諾書です。使用者が改葬に同意していることを証明する書類で、同じ場合は不要です。承諾書は市区町村の役所や役所のホームページで入手でき、無料で発行されます。
- 改葬承諾書は、使用者と改葬者が異なる場合に必要です。
- 役所やそのホームページで入手できます。
- 記入項目には、使用者と改葬者の住所・氏名・関係が含まれます。
- 発行費用は無料です。
- 市区町村によって様式が異なるため、事前に確認が必要です。
改葬承諾書が必要な場合、事前に役所で入手し、正確に記入してスムーズに手続きを進めましょう。
書類を提出し、改葬許可証を取得して提出する
「改葬許可証」は、改葬手続きを正式に進めるために役所から発行される重要な書類です。必要な書類をすべて揃えて役所に提出すると発行され、これを新しい霊園や墓地の管理者に提出します。書類に不備がないように、事前に確認しておきましょう。
- 改葬許可証は、お墓のある市区町村の役所で発行されます。
- 提出する書類には、受入証明書、改葬許可申請書、埋葬証明書、改葬承諾書(一部条件の方)があります。
- 発行費用は無料から300円程度です。
- 改葬許可証を改葬先の霊園や寺院に提出して納骨します。
改葬許可証を確実に入手し、新しい霊園や墓地での納骨手続きをスムーズに進めましょう。
閉眼供養を行い遺骨を取り出す
閉眼供養は、墓じまいをする際に行う仏式の儀式で、故人の魂を通常の状態に戻すために行います。菩提寺に依頼するか、近くのお寺に手配することができ、儀式は墓石の解体工事の前に行えます。
- 閉眼供養は魂を通常の状態に戻す儀式です。
- 菩提寺に依頼するか、近くのお寺に手配できます。
- 儀式は解体工事の当日より前に行うことが可能です。
- 読経はご僧侶によって行われます。
閉眼供養は大切な儀式なので、菩提寺やお寺に早めに依頼して準備を進めましょう。
石材店に墓石の解体と撤去を依頼する
墓石の解体・撤去は、専門の石材店に依頼して行います。費用は地域や業者によって異なりますが、一般的な相場は10万円前後です。作業を確認したい場合は、立ち会いも可能です。土地は更地にして返還するため、業者選びは慎重に行いましょう。
- 墓石の解体は専門の石材店に依頼します。
- 相場は10万円前後です。
- 作業の立ち会いが可能です。
- 土地は更地にして返還する必要があります。
慎重に業者を選び、墓石の解体・撤去を進めましょう。
墓地を原状回復し、返還する
墓石の撤去工事が終わったら、墓地を更地にして管理者に返還します。不完全な状態で返還するとトラブルになることがあるので、最後にしっかり確認しておくことが大切です。
- 墓地は更地にして返還します。
- 返還前に不備がないか確認します。
- 不完全な状態での返還はトラブルの元です。
- 返還後のトラブルを避けるため、注意深く確認します。
墓地を返還する前に、しっかりと最終確認を行い、トラブルを避けましょう。
新しい場所で遺骨の供養を行う
墓じまいが終わった後、遺骨は新しい改葬先に納めます。遺骨を運ぶ際は、骨壷が壊れないように注意し、公共交通機関や飛行機を利用する場合は、他の乗客やルールに配慮しましょう。
- 遺骨を運ぶ際は骨壷が壊れないように注意します。
- 公共交通機関を利用する際は配慮が必要です。
- 飛行機で運ぶ場合、航空会社のルールを確認します。
- 遺骨用の持ち運びバッグを使うと便利です。
遺骨を安全に運び、新しい改葬先で丁寧に供養しましょう。
墓じまいで気をつけるべきポイント

墓じまいは、感情的にも手続き的にも複雑な作業です。失敗しないためには、いくつかの重要なポイントに気をつける必要があります。このセクションでは、墓じまいを進める際に注意すべき点を詳しく解説します。事前にこれらのポイントを把握しておくことで、スムーズな手続きを進められます。
手続きは墓石撤去前に完了させる
墓じまいの行政手続きは、墓石の撤去工事が始まる前に終わらせることが重要です。手続きが完了していないと、撤去後の遺骨の納骨先が決まらず困ることになります。余裕を持って、墓石撤去の1か月前から書類の手続きを進めましょう。
- 行政手続きは、墓石の撤去前に終わらせることが大切です。
- 遺骨は撤去後に引き取りや発送が必要です。
- 納骨先が決まっていないと、遺骨の行き場がなくなります。
- 墓石撤去の1か月前から書類手続きを始めます。
手続きは早めに進め、墓石撤去に備えて万全の準備をしておきましょう。
改葬許可申請書は本人が記入する必要がある
改葬許可申請書は、本人が記入する必要がある重要な書類です。委任状があっても代行では記入できないため、忙しい方は事前に記入を済ませておくことが大切です。代行を頼む際に困らないよう、事前にしっかりと準備しておきましょう。
- 改葬許可申請書は本人が記入する必要があります。
- 委任状があっても、代行では記入できません。
- 事前に記入しておくことが大切です。
- 手続きがスムーズに進むよう、事前に準備します。
改葬許可申請書は本人が記入する書類なので、事前に記入を済ませ、手続きをスムーズに進めましょう。
改葬許可申請書は遺骨ごとに1枚ずつ記入する
改葬許可申請書は、遺骨1柱につき1枚記入する必要があります。お墓にある遺骨の数に応じて、申請書の枚数も増えるため、事前に必要な書類を揃えておきましょう。ただし、一部の役所では、1枚の申請書に複数の遺骨を記載できる場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
- 遺骨1柱につき、改葬許可申請書が1枚必要です。
- 遺骨の数に応じて申請書の枚数が増えます。
- 役所によっては、1枚に複数の遺骨を記載できる場合もあります。
- ホームページで事前に確認しておきましょう。
遺骨の数に応じた申請書を準備し、事前確認をしっかり行ってスムーズに手続きを進めましょう。
Auto Amazon Links: プロダクトが見つかりません。
まとめ:墓じまいを自分でやるための準備と手続きは?注意するポイントを知っておこう
墓じまいを自分で進めるには、事前にしっかりとした準備と手続きが必要です。お墓を守ることは大切なことですが、維持費や管理の負担が大きく、これを重荷に感じる方も多いのが現実です。そういった方々の助けとなるよう、墓じまいの具体的な流れや注意点を押さえておくことが大切です。
まず、親族との相談が必要です。墓じまいは感情的な問題が絡みやすいため、勝手に進めるのではなく、事前に親族全員に意向を伝え、同意を得ることが重要です。特に遠方に住んでいる親族にも必ず相談し、納得してもらうよう努めましょう。これにより、後々のトラブルを避けることができます。
次に、墓地の管理者やお寺に相談することが欠かせません。墓じまいには、現在のお墓を管理している方々の理解と協力が必要です。特に自分が檀家である場合は、お寺の収入にも関わるため、事前に丁寧に話を進めることが大切です。
また、遺骨の新しい供養方法や受け入れ先を決めることも重要です。永代供養墓や納骨堂、樹木葬などさまざまな選択肢がありますが、事前に調べて、親族と相談しながら最適な方法を選びましょう。さらに、墓石の解体や撤去を依頼する石材店の選定も必要です。解体費用は高額になることもあるため、複数の業者から見積もりを取って比較することが賢明です。
改葬手続きに必要な書類の準備も忘れずに行いましょう。改葬許可申請書や受入証明書、埋葬許可証などをしっかり揃え、役所に提出することで改葬許可証を発行してもらいます。これらの書類は遺骨の数に応じて必要な枚数が増えるため、事前に確認しておくと良いです。
さらに、墓石の撤去前には必ず手続きを完了させることが大切です。手続きが完了していないと、遺骨の納骨先が決まらないまま撤去されてしまうリスクがありますので、余裕を持って準備を進めることが求められます。
最後に、遺骨の取り扱いや供養についても慎重に進めることが大切です。移動中の遺骨が壊れないように注意し、公共交通機関や飛行機を利用する際は、他の方への配慮も忘れずに行いましょう。
以上の手順を丁寧に進めていくことで、スムーズな墓じまいを実現し、負担を軽減することができます。


私は墓の管理と墓じまいの専門家であり、10年を超える長きにわたり、墓の管理に困っている多くの家族に墓じまいの提案とサポートを行ってきました。
特に公営の墓地での一定期間の放置による墓の撤去や、墓の管理の困難さ、維持費の問題など、多くの家族が墓じまいを検討する理由はさまざまです。墓じまいの過程で必要となる墓地の管理者との相談や新しい供養の場所の選定など、これまでの経験を踏まえ、サポートするという視点で、墓の管理に困っている人を助けることができたらと感じています。