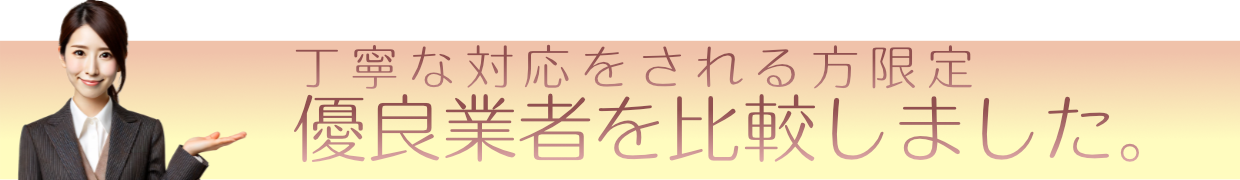更新日:2025年2月27日 | Tatsumi
墓じまいを検討している方にとって、墓じまいした後の土地の行方や売却の可否は大きな関心事です。
この記事では、墓じまいした後の土地はどうなるのか、売却は可能なのか、そして運営団体との関係について詳しく解説します。
墓地の運命や売却の実際、運営団体との取り決めなど、墓じまいに関する疑問を解消するための情報を提供します。
墓じまい後の土地の行方
墓じまいを行った後、その土地がどうなるのかは多くの方が気になるポイントです。特に、長年大切にしてきた場所だけに、その後の運命を知りたいと思うのは当然です。
墓地の売却は可能?
結論から申し上げますと、売却はできません。
墓じまいとは、墓地に存在する墓石を取り壊し、その土地を更地に戻して墓地運営者に返却することを指します。多くの人が、地元から離れて生活している、独身で後を継ぐ人がいない、先祖代々のお墓に入る予定がないなどの理由で墓じまいを検討します。しかし、墓じまいをした後の墓地を売却することはできないというのが現実です。
- 墓じまいの定義: 墓地にある墓石を取り壊し、土地を更地に戻して墓地運営者に返却すること。
- 墓じまいを検討する理由: 地元から離れて住む人、独身や後を継ぐ人がいない人、先祖代々のお墓に入る予定がない人などが墓じまいを検討する主な理由。
- 墓じまい後の遺骨の扱い: 遺骨は、合葬墓、納骨堂、樹木葬や海洋葬などの自然葬、あるいは手元供養として家に保管するなどの方法で扱われる。
- 墓地の価格: 墓地は非常に高価で、新しいお墓を建てる際や永代使用料には多額の費用がかかる。特に都心部の墓地は地価が高いため、更に高額になる。
- 墓地の売却: 墓じまいをした後の墓地を売却することはできない。過去の裁判例では、墓地の返還に関する訴えが退けられている。
墓じまいを行った後、墓地の売却はできないことを理解することは重要です。しかし、遺骨の扱い方や新しいお墓の選び方には多くの選択肢があり、それぞれの状況や希望に合わせて選ぶことができます。
何十年も寺院と契約をして、維持してきた土地ですが、売却はできないと裁判所の判決が出ている以上、売却することはあきらめましょう。仮に売却できたとしたら、墓の墓の間に、おかしなもの設置できるということになります。
仮に私有地の中に墓地がある場合、墓地は忌避施設と言って、特殊な建物に分類されるため、自治体に相談する必要があります。
墓地の返還と運営団体
墓じまいを行った後、墓地は運営団体に返還されることが一般的です。返還時に返還金が発生するかどうかは、契約内容や運営団体の方針によります。
墓じまいを検討する際には、土地の所有権や費用の負担など、重要なポイントをしっかり理解し、最適な選択を心がけましょう。
墓じまいの増加背景

近年、墓じまいの需要が増加している背景には様々な理由があります。それぞれの理由を深掘りし、墓じまいを検討する際の参考としてください。
お墓継ぐ人の減少
家族構成の変化や都市化の進行により、お墓を継ぐ人が減少しています。これが墓じまいの一因となっています。 都市部では核家族化が進行し、伝統的な家族墓を継ぐ人が少なくなってきています。
家族の形が多様化してきており、お墓を継ぐ人がいない家族が増えています。その結果、お墓の承継が難しくなり、墓じまいを選択する人が増えてきています。
- 生涯未婚: 一生独身で過ごす人が増えている。
- 子どもがいない夫婦: 子どもを持たない選択をする夫婦が増えている。
- 嫁いでいる娘のみ: 娘だけの家族で、娘が他家に嫁いでいる場合が増えている。
家族の形が変わる中、お墓の承継が難しくなる家族が増えてきています。そのため、墓じまいという選択が重要になってきています。
墓じまいをし、土地の対応について考える方はこのような方が多いことになります。未婚である、子供がいない夫婦である、子供が娘しかいないなどです。
墓参りの困難さ
現代の生活スタイルや働き方の変化により、定期的な墓参りが難しくなっています。
これも墓じまいの理由の一つです。 仕事や家庭の都合で墓参りの頻度が減少し、また、遠方に住む家族が墓参りをするのが難しいと感じるケースが増えています。
- 核家族化: 昔の大家族から核家族が主流となり、生まれ育った地域から離れるケースが増えている。
- 都市部集中: 人々が都市部に集まることで、地元から遠く離れた場所での生活が増えている。
- 両家のお墓の負担: 長男や長女が結婚すると、二つの家のお墓を守る負担が生じる。
- 遠方のお墓: 遠くのお墓は、特に高齢になると参拝が大変になる。
- 体力的な負担: 高齢者にとって、お墓の手入れや参拝が体力的に困難になることがある。
家族の形や生活の変化により、お墓参りが困難になるケースが増えており、これが墓じまいの選択の一因となっています。
いわゆる田舎にある墓へ、都会から子孫たちがわざわざ墓参りにくるという風習が廃れつつあります。デジタル化が進み、オンラインで顔を合わせることができ、いつでもつながることができる世の中だからこそ、墓参りの重要性が軽視されつつあります。良い悪いではなく、時代の流れなのです。
経済的背景
墓地の維持費や管理費が年々上昇しており、経済的な負担が増えています。墓地の維持にかかる費用や、新たな墓地の購入費用が高騰しているため、経済的な理由から墓じまいを選択する家族が増えているのです。
- 維持費の高さ: お墓の維持費や管理費、お寺へのお布施など、年間のコストが高くなっている。
- 家族の変化: 少子高齢化や核家族化の進行により、維持費を支払うのが困難に。
- 遠方のお墓: お墓が遠くにあると、子どもたちに負担をかけたくないという考えがある。
- 新しいお墓の検討: 墓じまい後に新しいお墓を考える人もいる。
- 昔の状況: 以前は家を継いだ人が維持費を支払っていたが、現在はその状況が変わっている。
経済的な負担や家族の変化が墓じまいの背景にあり、これを踏まえて新しいお墓の選択も考えられています。生涯年収が低くなっていく昨今、墓を維持するのにもお金がかかります。そのコストをずっとあと何年もかかりつづけるのか?を考えて墓じまいを検討する方が多いです。
墓じまいのステップ

墓じまいを進める際には、いくつかの手順を踏む必要があります。こちらでは、墓じまいをスムーズに行うためのステップを詳しく解説します。
関係者との相談
墓じまいをする前に、家族や親戚、墓地の管理者との相談が大切です。これにより、突然のお墓の変化に驚くことがなく、スムーズに手続きを進めることができます。
- 家族とのコミュニケーション: 家族との相談を先に行う。
- 親戚への報告: お墓参りに来る親戚への事前の相談と報告が必要。
- 墓地管理者との話し合い: 現在の墓地を管理している寺院や団体との連絡をとる。
- 後のトラブルを避ける: 事前の相談により、後での混乱やトラブルを避けることができる。
墓じまいをスムーズに行うためには、関係者とのしっかりとしたコミュニケーションが不可欠です。この親族との話し合いが難航する可能性が高いです。先祖代々守り続けてきたお墓をなくすということに対する嫌悪感が強い方もいるからです。
新しい納骨先の契約
次に、新しい納骨先を探し、契約を行います。新しい場所の選定は慎重に行うことが求められます。 信頼できる施設や寺院を選び、契約内容をしっかりと確認することが大切です。
- 新しい納骨先の選択: 現在の墓地内の納骨堂や永代供養塔、または新しい地域の墓地を選ぶことができます。
- 遺骨の状態の確認: お骨の状態や骨壺の数をしっかりと把握する。
- 墓地使用許可証の取得: 新しい墓地に移す場合、事前に「墓地使用許可証」が必要です。
- 納骨方法の選択: 1. お墓を建てる 2. 納骨堂や永代供養塔 3. 樹木葬などの方法から選べます。
墓じまいの際、新しい納骨先の選択と必要な手続きをしっかりと理解し、適切に進めることが大切です。新しい納骨先については、親族と話し合う必要があるでしょう。墓を管理している代表だけで決められることではないのが、トラブルを大きくしています。
必要な行政手続き
墓じまいをする際には、いくつかの行政手続きが必要です。これらの手続きは、新しい納骨先に移るための正式な許可を得るためのものです。
- 埋蔵の証明の取得: 現在の墓地管理者から「埋蔵の証明」をもらう。
- 改葬許可申請書の提出: 現在の墓地がある市町村に「改葬許可申請書」を出す。
- 改葬許可証の発行: 申請が認められると、「改葬許可証」がもらえる。
- 新しい墓地の場所の記入: 改葬許可証の中に、新しい墓地の場所を書くこと。
- 改葬許可証の保管: 新しい納骨先の墓地管理者に見せるため、大事に保管する。
墓じまいの手続きは、正しい順序で行うことが大切。そして、必要な書類は大切に保管して、新しい納骨先に提出することを忘れないようにしましょう。
事務的な手続きを忘れると、補助金が受けられなかったり、条例違反となったりしますので、注意しましょう。
遺骨の移動と墓じまい
墓じまいの最終段階では、遺骨の取り出しと墓石の撤去が行われます。この手続きは、新しいお墓に遺骨を移すためと、墓地をきれいに返すためのものです。
- 閉眼供養の依頼: ご住職にお願いして、「閉眼供養」を行ってもらう。
- 遺骨の取り出し: 供養が終わったら、遺骨をお墓から取り出す。
- 遺骨の移送: 取り出したお骨は、新しいお墓に運ぶ。
- 墓石の撤去: お骨が移された後、墓石を取り除く。
- 墓地の返還: 最後に、墓のあった場所をきれいにして、墓地管理者に返す。
墓じまいの際、遺骨の取り扱いと墓地の整理には細心の注意が必要。心を込めて手続きを進め、故人を新しい場所でしっかりと供養しましょう。
墓石を取り除く前に、開眼供養という、儀式があります。墓を全て撤去した後、土地を原状回復する必要があります。
新しい場所での納骨
新しいお墓に遺骨を納める際の手続きは、必要な許可と供養を行うことが大切です。
- 「改葬許可証」の提出: 新しい墓地管理者に「改葬許可証」を見せて許可を得る。
- 開眼供養の依頼: 住職にお願いして、新しいお墓で「開眼供養」を行ってもらう。
- 遺骨の納骨: 開眼供養が終わったら、新しいお墓に遺骨を納める。
- 供養の実施: 遺骨を納めた後、供養を行う。
新しいお墓に遺骨を納めるときは、正しい手続きと心をこめた供養が大切です。遺骨の移動先も親族どうして話し合いの上、決める必要があります。たった一人のために、決定ができないという法律的な制約はないものの家族間での関係性が悪くなる可能性もあるため、慎重にならざるを得ません。
Auto Amazon Links: プロダクトが見つかりません。
まとめ:墓じまいで後の土地はどうなる?

墓じまいを行った後、その土地がどうなるのかは多くの方が気になるポイントです。このセクションでは、墓じまい後の土地の運命について詳しく解説します。
墓じまいを検討する際、最も気になるのは、「墓地はどうなるのか」という疑問ですね。結論として、墓じまいを行った後の墓地は、多くの場合、運営団体に返還されます。
これは、墓地が特定の家族や個人のために確保されているため、他者に転売することが許されないからです。また、墓地の売却は基本的に認められていないため、墓地を管理している団体や寺院に返還するのが一般的です。
ただし、一部の運営団体では、墓地の返還時に一定の返還金を支払う場合もあるため、具体的な条件や手続きは、各団体や寺院に直接問い合わせることが必要です。
墓じまいは、家族の歴史や思い出と向き合う大切なプロセスです。墓じまい後の土地の行方を知ることで、家族全員が納得のいく形で新しいスタートを切ることができるでしょう。
墓を売った費用などを検討している方は、返還することが義務であるため、難しいと覚えておくと良いでしょう。この記事が墓じまいを検討されている方の役に立ちますように。

私は墓の管理と墓じまいの専門家であり、10年を超える長きにわたり、墓の管理に困っている多くの家族に墓じまいの提案とサポートを行ってきました。
特に公営の墓地での一定期間の放置による墓の撤去や、墓の管理の困難さ、維持費の問題など、多くの家族が墓じまいを検討する理由はさまざまです。墓じまいの過程で必要となる墓地の管理者との相談や新しい供養の場所の選定など、これまでの経験を踏まえ、サポートするという視点で、墓の管理に困っている人を助けることができたらと感じています。