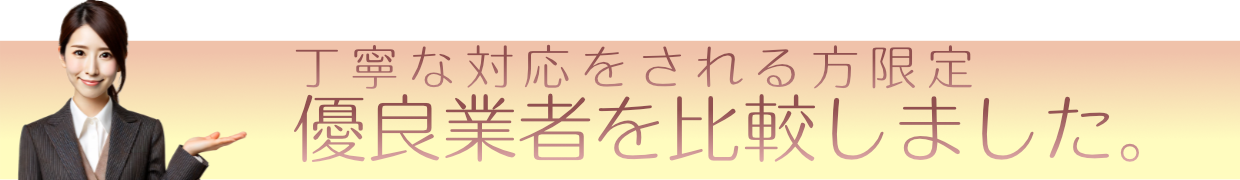更新日:2025年2月27日 | Tatsumi
墓じまいを検討している方々の中には、「墓じまいをしないとどうなるの?」という疑問を持っている方も多いでしょう。
私も墓を管理しないといけない世代です。墓を守りなさい!と言われた時代は終わりを告げようとしています。墓を維持しないからといって、先祖を敬っていないとか、祟りがあるとか言われていますが、時代の変化によって、墓のあり方も変化しています。
この記事では、墓じまいをしない場合のリスクや影響、そして墓じまいをした方が良い具体的なシチュエーションについて詳しく解説します。墓の未来や家族への影響を考慮して、適切な選択をするための情報を提供します。
お墓を放置するとどうなるのか?

お墓を放置すると、さまざまな問題が生じる可能性があります。特に、公営や民営の墓地、寺院の墓地での放置は、それぞれ異なる影響が考えられます。
ここでは、それぞれの場合にどのような影響が出るのか、具体的に解説していきます。
公営や民営の墓地での放置の影響
公営や民営の墓地では、お墓を放置してもすぐに撤去や墓じまいが行われることは稀です。
公営の墓地は税金を使用して撤去活動を行うため、予算の制約から多くのお墓を一度に撤去することは難しい状況です。
一方、民営の墓地では、墓地の空きスペースがある限り、管理料の滞納があってもお墓が勝手に撤去されることは少ないです。ただし、管理料の支払いを続けて無視すると、法的な問題が生じる可能性があります。
- 公営の墓地は、税金での撤去活動が限られている。
- 民営の墓地は、空きスペースがある限り撤去は少ない。
- 管理料の滞納は、法的な問題を引き起こす可能性がある。
お墓の放置には注意が必要ですが、すぐに撤去されることは少ない。それでも、管理料の支払いは適切に行うことが重要です。
今現在維持している墓はどこに属しているのか?をまずは確認しましょう。それによって、対応方法が変わってきます。
寺院の墓地での放置の影響
寺院におけるお墓の取り扱いは、寺院ごとに異なります。一部の寺院では、古くからの土葬の考えに基づき、お墓を放置しても問題ないとの考えを持っています。
しかし、すべての寺院がこのような考えを持っているわけではありません。放置されたお墓は、一定の期間が経過すると、解体や撤去の対象となることも考えられます。
- 寺院の中には、お墓の放置が許容されるところもある。
- 一部の寺院では、放置されたお墓を一定期間後に解体・撤去する場合がある。
- お墓の継承や放置については、寺院に事前に相談することが大切。
寺院ごとにお墓の取り扱いが異なるため、事前の相談が重要です。どの宗派というよりは、どのお寺が管理しているか?を確認し、意向を聞いてみましょう。
お墓を放置した場合のリスク

お墓を放置することは、予想以上のリスクを伴います。特に、無縁仏となる可能性や公営墓地での撤去が考えられます。
ここでは、それぞれのリスクについて詳しく解説し、墓じまいを検討している方々が適切な判断を下せるような情報を提供します。
無縁仏となるリスク
お墓を放置し続けると、遺族や親戚が供養を行わなくなり、結果として無縁仏となるリスクが高まります。
お墓の管理費は、墓地の維持や施設の管理のためのもので、お墓の掃除やお手入れに使われるわけではありません。管理費を滞納すると、催促があり、さらに放置するとお墓が撤去される可能性があります。撤去された後のご遺骨は、他の無縁仏と合祀されることが多いです。
- お墓の管理費は、墓地の維持や施設の管理のためのもの。
- お墓のお手入れは、所有者の責任。
- 管理費の滞納が続くと、立て札や官報への掲載が行われる。
- 連絡を放置し続けると、お墓が撤去される可能性がある。
- お墓が撤去された後のご遺骨は、他の無縁仏と合祀されることが一般的。
管理費の滞納や連絡の放置は、お墓の撤去や合祀のリスクを高めるため、注意が必要です。相続後誰も引き継ぎたくなく放置していたとしても、相続権が放棄されない限り、管理費の支払いが相続人に引き継がれるのが通常です。
公営墓地での撤去の可能性
公営の墓地では、一定の期間お墓を放置すると、墓地の管理者から撤去の通知が来ることがあります。
公営の墓地や民間の霊園では、お墓を放置してもすぐに撤去されることは少ないです。公営の墓地の撤去には税金が使われるため、予算の制約からすぐには行われないことが多いです。
しかし、管理費の滞納や放置は、撤去のリスクを伴うため注意が必要です。
- 公営の墓地の撤去には税金が使われる。
- お寺の墓地は区画に限りがあるため、放置すると撤去のリスクが高い。
- 民間の霊園では、空きがある限りすぐには撤去されない。
- 管理費の滞納は撤去のリスクを伴う。
- お墓を放置することは、撤去される理由にはならない。
お墓の放置や管理費の滞納は、撤去のリスクを伴うため、適切な対応が必要です。放っておけば勝手に撤去されると考える方が多いようですが、税金が使われていることを考えると、しっかりと決断し、墓じまいの対処をする必要があります。
墓じまいを検討すべき状況

墓じまいを検討するタイミングは人それぞれですが、特定の状況や条件下では、墓じまいを考えることがより一層重要になります。
以下では、墓じまいを検討すべき具体的な状況を詳しくご紹介します。
お墓の管理が難しい場合
お墓の管理は時間と労力がかかるもの。特に、雑草の手入れや墓石の清掃など、定期的なメンテナンスが必要です。
高齢になると、お墓の管理が難しくなることがあります。体力の低下や足腰への負担など、様々な理由でお墓の掃除や訪問が困難になることがあるため、墓じまいを検討する方が増えています。
- 体力の低下でお墓の掃除が難しくなる。
- 足腰への負担でお墓までの訪問が困難に。
- 高齢になると、近場のお墓であっても訪問が難しくなることがある。
- 草むしりや落ち葉集めなどの掃除は特に負担が大きい。
- 掃除の困難さを感じると、墓じまいを検討する方が増えている。
高齢になるとお墓の管理が難しくなるため、その時期を見越して墓じまいの検討が必要です。また、病気をされた場合は、一気に墓への訪問が億劫になり、放置気味なるでしょう。管理者の年齢の問題も考慮しておく必要があります。
お墓の維持費が重荷になっている場合
お墓の維持には、管理費や供養費などの経費がかかります。
お墓の管理費は、墓地の維持や設備の管理に使われていますが、これが経済的な負担と感じる場合、墓じまいを検討することが考えられます。
- お墓の管理費は、墓地の清掃や整備に使われる。
- 掃除用具の管理や水道料金も管理費に含まれる。
- お墓がある限り、管理費の支払いは避けられない。
- 経済的な負担を感じる場合、墓じまいを検討する価値がある。
管理費が経済的な負担となる場合、その負担を軽減するために墓じまいを検討する方が多いです。家族に金がかかる、仕事がうまくいかないなどの問題で、墓じまいを検討する方が増えています。
お墓が遠くにある場合
遠方にお墓があると、定期的なお参りや管理が難しくなります。移動の手間や交通費も考慮すると、墓じまいを検討し、もっと身近な場所に供養の場を移すことが良い選択となるかもしれません。
特に遠距離で頼れる親戚もいない場合、墓じまいを考えるタイミングかもしれません。
- お墓参りは、お墓の近くに住んでいないと難しい。
- 新幹線や飛行機を使っての移動が必要な場合、頻繁には訪れられない。
- 頼れる親戚がお墓の近くにいない場合、放置期間が長くなるリスクがある。
- お墓の管理や手入れが難しい場合、墓じまいを早めに検討することが考えられる。
住んでいる場所がお墓から遠い場合、定期的なお墓参りや管理が難しくなるため、墓じまいを検討することが推奨されます。
遠方にある場合は、交通費もバカになりません。車で数時間の距離なんて場合は、墓じまいを検討するタイミングかもしれません。
子どもや家族に負担をかけたくない場合
家族や子どもにお墓の管理や供養の負担をかけたくないと考える方も多いです。このような思いから、自らの意思で墓じまいを選択することで、後世への負担を減少させることができます。
しかし、家族や親族の中には墓じまいに反対する人もいるため、事前の話し合いが大切です。
- お墓の管理の負担を子どもにかけたくないという思いがある。
- しかし、家族や親族の中に墓じまいに反対する人もいる。
- 墓じまいを検討する場合、家族や親族との事前の話し合いが必要。
- 子どもや親族の意見や感情を尊重し、許可を取ることが大切。
お墓の管理の負担を子どもにかけたくない場合でも、家族や親族との事前の話し合いと理解が必要です。これからどんどん子供は墓から離れる生活をしていく可能性が高くなります。
もしかしたら、海外で暮らすのが一般的になると定期的にメンテナンスすることは難しくなります。
お墓を継ぐ人がいない場合
家族構成や状況によっては、お墓を継ぐ人がいない場合があります。このような状況では、無縁仏になるリスクが高まります。
子どもがいない、または独身でお墓を継いでくれる人がいない場合、お墓が荒れ果てるリスクが高まります。
- 子どもがいない、または独身の人はお墓の継承者がいない可能性が高い。
- 継承者がいないお墓は、時間とともに荒れてしまうことがある。
- お墓が荒れる前に、墓じまいを検討することで、無縁仏のリスクを避けられる。
- お墓の状態を良好に保つための継承者がいない場合、墓じまいが一つの選択肢となる。
継承者がいない場合、お墓が荒れるリスクが高まるため、墓じまいを早めに検討することが大切です。相続の問題は生きているうちに解決するのがスムーズです。墓を継承する場合は、契約されていた方が亡くなった場合は、その手続きを先にしない墓じまいができなくなりますので注意しましょう。
墓じまいの手順

墓じまいを行う際には、いくつかの手順を踏む必要があります。ここでは、墓じまいの具体的な手順とそのポイントをわかりやすく解説します。
適切な手順を踏むことで、スムーズに墓じまいを進めることができます。
墓地の管理者への相談
墓じまいを考えている場合、まずは墓地の管理者に相談することが大切です。
墓じまいをする際、まずは墓地の管理者や菩提寺に連絡をして、その意向を伝えることが大切です。その際、菩提寺の了解や閉眼供養の手配など、いくつかの手続きが必要となります。
- 墓じまいをする前に、墓地の管理者や菩提寺に連絡を取る。
- 管理者の了解が必要。
- 家が檀家の場合、離壇することになる可能性がある。
- 菩提寺の僧侶に閉眼供養をお願いすることも考えられる。
新しい供養の場所の選定
墓じまいを行った後、故人の供養を続けるための新しい場所を選ぶ必要があります。寺院や納骨堂など、様々な供養の場所が考えられるので、家族で話し合いながら選ぶと良いでしょう。
墓じまいを考える際、遺骨をどこに納めるか、新しい供養の場所をしっかりと選ぶことが大切です。いくつかの供養方法があり、それぞれの方法によって供養の形が異なります。
新しい供養先の選択肢:
- 樹木葬
- 納骨堂
- 散骨
- 永代供養墓
- 手元供養
墓石の解体業者の選び方
墓石の解体や撤去は、専門の業者に依頼することが一般的です。信頼性や実績を重視して、適切な解体業者を選ぶことが大切です。
墓石解体のポイント:
- 石材店が解体の主な業者として知られています。
- 複数の業者から見積もりを取ることで、適切な費用を知ることができます。
- 一部の墓地や霊園では、指定の石材店を利用する必要があるかもしれません。
- 解体にかかる費用は、おおよそ10万円前後となることが多いです。
必要な書類の手続き
墓じまいや新しい場所への納骨には、いくつかの書類手続きが必要です。必要な書類は自治体によって異なることがあるので、しっかりと確認しましょう。
書類手続きのポイント:
- 受入証明書:新しい場所での受け入れを証明する書類です。
- 改葬許可申請書:墓じまいの許可を求めるための書類です。
- 埋葬証明書:遺骨が埋葬されていたことを示す書類です。
- 各自治体のホームページで、必要な書類の詳細を確認できます。
閉眼供養と遺骨の取り扱い
閉眼供養は、お墓に眠る故人やご先祖の魂をお墓から移す行事です。特に仏教の場では、この供養を行わないと墓の解体が許可されないことが多いです。
供養が終われば、遺骨を取り出し、お墓の解体や撤去が進められます。
閉眼供養のポイント:
- 閉眼供養は「魂抜き」とも言われます。
- 仏教の場では、閉眼供養を行わないと墓の解体が難しいことが多いです。
- 供養が終わった後、遺骨を取り出すことができます。
- その後、お墓の解体や撤去が進められます。
お墓の解体と撤去
お墓の解体工事は、解体専用の業者に依頼するステップです。
しかし、業者の選び方や費用には注意が必要です。指定の業者があるか確認し、複数の業者から見積もりを取ることで、適切な費用での依頼が可能となります。
トラブルを避けるためにも、墓地管理者との相談をしながら慎重に進めることが大切です。解体をして、トラックに積み込まれ、運ばれて最終的に粉砕されます。
新しい場所での納骨
墓じまいの最後のステップは、新しい供養先に遺骨を納めることです。事前に選んだ場所で、故人の魂を安らかに休ませることができます。
これで最後のステップです。
新しい供養先での納骨のポイント:
- 事前に選んだ供養先に遺骨を移す。
- これで墓じまいの手続きは終了。
- 新しい場所で故人を安らかに休ませる。
Auto Amazon Links: プロダクトが見つかりません。
まとめ:お墓を放置するとどうなるのか?
お墓を大切に思う気持ちは、多くの人が共有するものです。しかし、さまざまな事情でお墓を放置することが考えられる場面もあるでしょう。
そんな時、放置の結果としてどんな影響が考えられるのか、しっかりと理解しておくことは大切です。
お墓を放置すると、無縁仏となるリスクが高まります。
特に公営の墓地では、一定期間放置されたお墓は撤去の対象となることがあります。また、お墓の管理が難しくなったり、維持費が重荷となる場合、墓じまいを検討することが考えられます。
墓じまいを行う際には、墓地の管理者への相談や新しい供養の場所の選定など、いくつかの手順を踏む必要があります。
お墓を放置することは、故人への敬意や家族の気持ちを考えると避けたい事態です。
墓じまいを検討する際は、適切な手順を踏みながら、故人の魂を安らかに供養する方法を選ぶことが大切です。
墓のことは頭の片隅にあっても、なかなか行動に移すのは難しいです。実際自分が管理をすることになって初めて気がつくことでしょう。
今までこんな大変な管理を先人たちはしてきたのか?と思うととても苦しい気持ちになります。今生きている人よりも、亡くなった方の方が多い世界です。故人を敬えと言われますが、本当の意味で敬うとはどういうことでしょうか?
一人一人感覚は違うと思い、100%の正解はありません。だからこそ、家族が協力しあって、一番負担の少ない方法で墓じまいをできれば良いですね。

私は墓の管理と墓じまいの専門家であり、10年を超える長きにわたり、墓の管理に困っている多くの家族に墓じまいの提案とサポートを行ってきました。
特に公営の墓地での一定期間の放置による墓の撤去や、墓の管理の困難さ、維持費の問題など、多くの家族が墓じまいを検討する理由はさまざまです。墓じまいの過程で必要となる墓地の管理者との相談や新しい供養の場所の選定など、これまでの経験を踏まえ、サポートするという視点で、墓の管理に困っている人を助けることができたらと感じています。