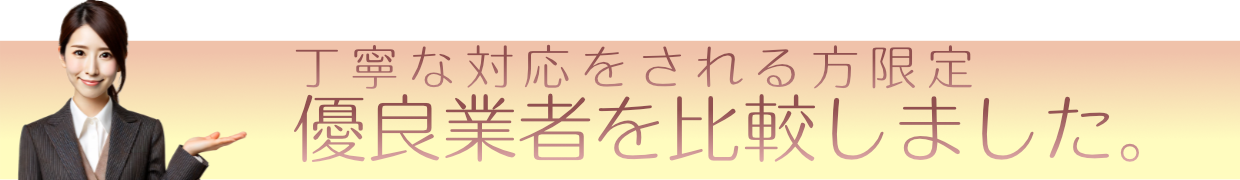更新日:2025年2月27日 | Tatsumi
墓じまいを検討している方々へ。生活保護を受けている中で、お墓の費用が払えないという悩みを持つ方は少なくありません。
この記事では、費用が払えない時の具体的な対処法や、補助金の存在について詳しく解説します。お墓のことは、後回しにしてしまいがちですが、しっかりとした知識を持って、適切な対応をとることが大切です。
お墓を放置するとどうなるのか?

お墓を放置してしまうと、どのような影響があるのでしょうか。お墓の管理が困難になったり、長期間放置されると墓地の管理者や寺院から撤去の通知が来ることも。
特に、お墓の場所によっては、一定期間放置すると無縁仏として取り扱われ、撤去されるリスクも高まります。
また、自治体によっては、放置されたお墓の撤去や管理に関するルールや手続きが定められている場合も。例えば、一部の自治体では、放置期間が一定を超えると、撤去の許可を得るための手続きが必要となります。
このように、お墓を放置することは、後の手間やコストが増えるだけでなく、故人を偲ぶ場所が失われることも考えられます。しっかりとした知識を持ち、早めの対応が大切です。
お墓を放置すると、いくつかの手続きや結果が生じます。以下に、その主なポイントをリスト形式でまとめました。
- お墓や納骨堂を放置すると、管理者によって強制的に撤去されることがあります。
- お墓が撤去される前に、官報に申し出のお知らせが掲載されます。
- その後、墓地の目立つ場所に立て札が設置され、1年間掲示されます。
- 1年間、申し出がない場合、お墓は無縁の墓として扱われ、撤去の手続きが進められます。
- 無縁の墓となった遺骨は、他の遺骨と合祀されるため、後から取り出すことはできません。
お墓を放置すると、一連の手続きを経て最終的には強制撤去される可能性があります。適切な手続きや管理を心がけましょう。
「お金がないからしょうがないじゃないか!」という生活保護の方もいるかもしれません。ただ、現在の日本の対応では上記のようなものが一般的です。自分だけの問題ではなく、親族全員に関連してくる問題なので注意しましょう。
生活保護を受けている方の墓じまいについて

生活保護を受けている方々が墓じまいを考える際、多くの疑問や不安が生じることがあります。
特に、後継者がいない場合や、補助金の存在、市民課との交渉方法など、知っておくべきポイントが多数存在します。この記事では、それらの疑問点を明確にし、具体的な対応策を提案します。
後継者がいない方が多い理由
近年、核家族化が進む中で、後継者がいない家庭が増えています。高齢化が進む日本では、子供の数が減少し、一人暮らしの高齢者も増加しています。
このため、お墓の後継者が不在となるケースが増えているのです。
生活保護を受けている方の中には、一人で生活している方が多く、後継者や親しい家族がいない方も少なくありません。以下に、その主な状況をリスト形式でまとめました。
- 生活保護を受けている方の中で、一人暮らしをしている方が多い。
- お墓があっても、後継者や家族がいないため、お墓の管理が難しい。
- ご先祖様を無縁の墓にしたくないという思いが強い。
- しかし、そのような状況を変えるのが難しいのが現状。
後継者や家族がいない方は、お墓の管理や後のことを考えると、様々な悩みや困難があることを理解し、サポートの方法を考えることが大切です。
「お金がないから無理!」「親戚からの信用がないから無理!」とあきらめる前に、信頼できる相談者に問い合わせて見るのも一つの方法です。
無縁仏のリスク
お墓を放置すると、無縁仏となるリスクが高まります。無縁仏とは、お墓の管理や供養をする人がいないため、お墓が放置される状態を指します。これにより、墓地の管理者から撤去の通知が来ることも。
- 今の状態が続くと、無縁仏のリスクが高まる。
- ご先祖様を放っておくことに対する気持ちの葛藤がある。
- 早めの対応や手続きを進めることで、無縁仏を避けることができる。
- どんなに努力しても解決しない場合、ご先祖様も理解してくれると信じている。
無縁仏のリスクを避けるためには、早めの対応や情報収集が大切です。心の中での思いや気持ちも、行動に移す一歩として大切にしましょう。
先祖を敬いましょう、しっかりやらないとバチが当たる。といったことを言う親族の方もいるかもしれません。この無縁仏はお盆時に買ってくるお墓がなくなり、子孫への関係性がなくなることを意味しており、人によっては忌み嫌われる対応の仕方にです。
墓じまいの補助金について
一部の自治体では、墓じまいの際の費用を補助する制度が設けられています。この補助金を利用することで、経済的な負担を軽減することが可能です。
以下は、一つの例です。
- 市川市営霊園では「一般墓地返還促進事業」として、墓地返還者に補助金を支給。
- 補助金の金額は、墓地の大きさによって異なり、12㎡の墓地で44万円など、大きな金額が支給される。
- 墓地が不足している自治体では、返還された墓地を再整備して再販する取り組みがある。
- 墓地返還は、使用者にとっても市にとっても双方にメリットがある。
- 霊園が満杯の自治体では、墓地返還は非常に有り難いとされている。
墓じまいを検討している方は、自身の住む自治体の補助金制度を確認し、適切に交渉することで、墓じまいの負担を軽減することができます。
今現在、存命となっている人よりも、亡くなられた数の方が多いのは当たり前です。ともすると、それだけお墓の場所が必要になっていると言うことで、自治体によっては墓じまいを歓迎する場合もございますので、問い合わせをしてみましょう。
市民課との交渉方法
墓じまいの際には、市民課との交渉が必要となることがあります。
後継者がいないお墓は、放置されると様々な問題が生じます。以下に、その主な内容と対応策をリスト形式でまとめました。
- 後継者がいないお墓は、無縁仏のリスクが高まります。
- お墓の放置は、周りの方や霊園事務所、行政に迷惑をかける可能性があります。
- 墓じまいにはまとまったお金が必要ですが、補助金の制度を利用することで、自己負担を減らすことができる場合があります。
- 公営の霊園では、行政も墓地の放置に困っているため、交渉により解決策を見つけることが期待できます。
墓じまいの際には、行政や関連機関との交渉を積極的に進めることで、補助金やサポートを受けることが可能です。早めの相談が大切です。
また、ご自身で相談できない場合でもNPO法人やボランティアのサービスも存在しているので問い合わせをしてみると良いかもしれません。
体力がある方へのサポート
墓じまいには様々な方法がありますが、身体が動く方であれば、自分で墓を片付ける選択も考えられます。しかし、専門的な知識や技術が必要な場合もあるため、適切なサポートを受けることをおすすめします。
- 家の裏にお墓がある場合など、特定の状況で自分で墓を片付けることが考えられます。
- 一般的な墓じまいでは、事故のリスクがあるため、専門家のサポートが必要です。
- 自分で墓を片付ける場合、石を小さく割る作業が必要です。必要な道具は貸し出し可能です。
- 割った石は、クレーンが近づける場所まで運ぶことが求められます。
- 地下のコンクリート部分の撤去にも、道具の貸し出しがあります。
- 作業には1か月程度の時間がかかる可能性があります。
- 石材の道具は消耗品なので、費用の負担が必要です。また、石やコンクリートの処分にも費用がかかります。
身体が動く方で、自分で墓じまいを行いたい意思がある場合、適切なサポートと注意点を理解した上で、安全に作業を進めることが大切です。
ただし、お墓を撤去する前に、しっかりとした儀式をしておく必要があり、自治体の許可なしでは遺骨を取り出してはいけないことになっています。
墓じまいの費用が払えないときの対応方法

墓じまいを考える際、費用の問題は避けて通れない課題となります。特に、経済的な困難を抱えている方は、どのように対応すればよいのか迷うことも。
費用が払えないときの具体的な対応方法を詳しく解説します。
家族や親族との相談
墓じまいの費用については、まず家族や親族と相談することが大切です。
墓じまいの際、費用の問題や手続きについて悩むことがあるかもしれません。そんなときは、以下のステップを参考に、家族や親族との相談を進めてみてください。
- 話し合いの場を設ける:まずは家族や親族を集めて、墓じまいについての話し合いの場を持ちましょう。
- 費用の問題を共有する:墓じまいの費用についての悩みや不安を正直に話すことが大切です。
- 皆での協力を求める:お墓は家族全体のもの。皆で協力して費用を工面する方法を考えることができます。
- 墓じまいの意義を理解してもらう:墓じまいに対するマイナスの印象を持つ人もいるかもしれません。そのため、墓じまいの意義や必要性をしっかりと伝えることが大切です。
墓じまいの際は、一人で悩むよりも家族や親族とのコミュニケーションを大切にし、共に解決の道を探ることが心の負担を軽減する鍵となります。
家族が不仲であると、協力できないといって、突っぱねられてしまう可能性はあります。毎年できるかぎりしっかりとしたコミュニケーションをしていくことで、決断する時に協力を得ることができるでしょう。
費用を抑える改葬方法の選び方
改葬方法を選ぶ際、費用を抑えるためのポイントがいくつか存在します。
墓じまいを考える際、費用の問題は避けて通れないものです。以下のステップを参考に、できるだけ費用を抑える改葬方法を選ぶことができます。
- 改葬方法の調査:まずは、費用を抑えられる改葬方法を探しましょう。
- 近場の墓地を選ぶ:自宅から近い墓地を選ぶことで、移動の費用や手間を省くことができます。
- 墓石と土地の違いを理解する:墓石は自分たちのものですが、土地は霊園や墓地管理者のもの。この違いを理解することで、必要な費用を正確に把握することができます。
- 土地の広さを考慮する:お墓の広さや地代によって、管理費が変わることがあります。適切な広さの土地を選ぶことで、長期的な費用を抑えることができます。
改葬を行う際は、事前の情報収集と計画が大切です。適切な方法を選ぶことで、心と財布の負担を軽減することができます。生活保護を受給しており、貯金もあまりないと言う方は、まず補助金ありきでの業者への依頼になってくると思います。その旨しっかりと業者に伝えることでトラブルなしに検討できるでしょう。
お手頃価格の業者を探す方法
墓じまいの業者選びは、費用の面で大きな影響を持ちます。信頼性とコストのバランスを考慮しながら、お手頃価格の業者を探す方法を紹介します。
- 複数の業者に見積もりを依頼:一つの業者だけに頼らず、複数の解体業者に見積もりを出してもらうことで、適切な価格を知ることができます。
- 指定の解体業者があるか確認:お墓によっては、指定の解体業者がある場合も。その場合、他の業者に依頼することが難しいかもしれません。
- 解体費用に納得する:見積もりをもとに、納得のいく費用で契約を結ぶことが大切です。
- 石材店の請求額を確認:石材店からの解体に関する請求が高額な場合、他の業者と比較してみると良いでしょう。
お墓の解体は大切な作業です。複数の業者に見積もりを取り、納得のいく業者を選ぶことで、心の負担も軽くなります。ただし、安易に何社も見積もりを同時に取るのはやめましょう。業者への失礼がないように、見積もりを取ることが大切です。わざわざきてもらって、結局依頼しないとなると、業者も赤字なので、信頼関係が崩れてしまいます。
自治体への相談の進め方
費用の問題で困っている場合、自治体に相談することも一つの方法です。
お墓の維持や解体にかかる費用は、思ったよりも高くなることがあります。しかし、自治体によっては、墓じまいをサポートするための補助金や助成金を提供している場所もあります。
以下参考として、ご覧ください。
- 千葉県市川市の取り組み:経済的な理由や後継者がいない場合、墓じまいを行う方に対して、一定の金額の返還や助成金を提供しています。
- 群馬県太田市のサポート:無縁墓地の対策として、墓地返還時の墓石撤去費用の助成を行っています。
- 自治体への相談:お住まいの自治体に、墓じまいに関する補助金や助成金の情報があるか確認してみると良いでしょう。
お墓の維持や解体に関する費用のサポートは自治体によって異なります。自分の住む自治体のサポート内容を確認し、適切なサポートを受けることが大切です。
あなたはどちらにお住まいですか?市役所の窓口に相談してみるのも一つの方法です。どのような方法があるか模索しましょう。
両家墓としての活用方法
両家墓とは、複数の家族で共同で使用する墓のことを指します。この方法を採用することで、墓地の維持管理費や墓じまいの費用を共同で分担することが可能となり、経済的な負担を軽減することができます。
- 経済的なメリット:新しいお墓を建てる必要がなく、管理費用も抑えられます。
- お墓参りの効率化:一度にお墓参りや管理ができるので、手間が省けます。
- 後継者の問題の解消:お墓の承継者がいない場合の悩みを解消できます。
- 事前の相談が大切:親族間での合意や、墓石の名前など、後からトラブルにならないように事前にしっかりと話し合うことが必要です。
- 規約の確認:墓地や霊園によっては、両家墓が禁止されている場合があります。また、宗派によっては改宗が必要な場合もあるので、事前に確認をとることが大切です。
両家墓は経済的なメリットや効率化が期待できる一方で、事前の相談や規約の確認が欠かせません。親族そして、霊園との話し合いをしっかりとする必要があります。
生活保護でお金がない場合は、親戚の中に他の親族がいる場合は、対象となる可能性があります。負担率も考慮して検討しましょう。
Auto Amazon Links: プロダクトが見つかりません。
まとめ:生活保護受給者が墓じまいを検討するには?

生活保護を受けている方が墓じまいを検討する際、さまざまな課題や疑問が浮かび上がることがあります。この記事では、そのような方々が墓じまいを進める上でのポイントや注意点をまとめました。
生活保護を受けている方が墓じまいを考える際、まずは家族や親族との相談が大切です。
経済的なサポートや意見交換を通じて、最適な方法を見つけることができます。また、墓じまいに関する費用は、自治体の補助金やサポートを利用することで、軽減することが可能です。
一部の自治体では墓じまいの費用を補助する制度がありますので、詳しく調査してみると良いでしょう。また、墓じまいの業者選びも重要なポイントとなります。信頼性とコストのバランスを考慮しながら、適切な業者を選ぶことが求められます。
墓じまいを検討する際は、しっかりとした情報収集と計画を立てることが大切です。生活保護を受けている方でも、適切なサポートや情報をもとに、スムーズに墓じまいを進めることができます。
誰しも生活保護を受けたくて受けているわけではありません。
墓を維持するのは大変な負担となる場合があります。遠方にあったり、維持費がかかったりすると、なお負担は大きいでしょう。墓じまいをしたいタイミングで生活保護になってしまった場合は、あきらめなくてはいけないのか?と考える方も多いですが、方法はいろいろありますので、確認していくと良いでしょう。

私は墓の管理と墓じまいの専門家であり、10年を超える長きにわたり、墓の管理に困っている多くの家族に墓じまいの提案とサポートを行ってきました。
特に公営の墓地での一定期間の放置による墓の撤去や、墓の管理の困難さ、維持費の問題など、多くの家族が墓じまいを検討する理由はさまざまです。墓じまいの過程で必要となる墓地の管理者との相談や新しい供養の場所の選定など、これまでの経験を踏まえ、サポートするという視点で、墓の管理に困っている人を助けることができたらと感じています。