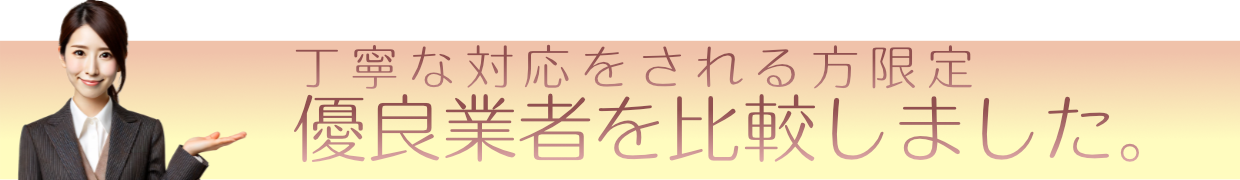更新日:2025年2月27日 | Tatsumi
墓じまいを検討している方へ。お布施はいつ渡すのが正しいのでしょうか?また、相場やその他の費用、タイミングやマナーについても気になりますよね。
この記事では、「墓じまいのお布施」に関する疑問を解決します。初めての方でも安心して進められるよう、わかりやすく解説しています。
墓じまいとお布施の基本
墓じまいとは、長い間大切にしてきたご先祖の墓を整理すること。そして、その際に渡すお布施の意味やマナー、法的な背景についても知っておきたいですよね。このセクションでは、それらの基本的な情報を優しく、わかりやすくご紹介します。
墓じまいって何?
墓じまいは、家族の墓を永代供養墓や合同墓地に移すことを指します。
墓じまいは、大切な先祖のお墓を整理し、その土地を元の状態に戻す行為です。お墓を整理した後、故人の遺骨は新しい場所や方法で大切に供養します。ただし、墓じまいを進める前には、必要な手続きをきちんと行うことが大切です。
墓じまいのポイント
- 故人の遺骨は、新しいお墓や納骨堂などに移すことが基本です。
- 墓じまい後、墓地の使用権は管理者に返す必要があります。
- 墓じまいをする際には、行政の手続きが必須です。
- 遺骨を勝手に移すのは法律で禁止されています。
墓じまいは故人を大切に思う心からの行為。しかし、適切な手続きをしっかりと行わないと法的な問題が生じる可能性があるので、注意が必要です。
維持費や管理が難しくなってくるにつれ、墓を手放す、つまりは墓じまいを検討される方が多くなっています。故人を敬うことは大切ですが、現代では墓を止めるという方法を取る方が増えています。
お布施の本当の意味
お布施は、仏教における修行の一環として、感謝や尊敬の気持ちを表すためのものです。
お布施は、お寺や僧侶に対する感謝の気持ちを表すためのものです。法的な義務や決まった金額はなく、心からのお礼としての寄付的な要素が強いです。
お布施のポイント
- お布施は、お寺や僧侶への「お礼の気持ち」を示すためのものです。
- 法的な根拠や支払い義務はないので、金額は「お気持ちで」とされることが多いです。
- ただし、墓じまいの際には、仏様を取り出すので、閉眼供養が必要です。
- これまでの感謝の気持ちを伝えるため、お布施は気持ちよく渡すべきです。
- 単に墓石をどけて終わりというわけにはいかないので、適切な手続きと感謝の気持ちが大切です。
お布施は、お寺や僧侶への深い感謝の気持ちを示す大切な行為。心からのお礼として、適切な手続きとともに渡すことが大切です。
もしかしたら、今まで高い管理費を支払って維持してきたのに、墓じまいをするときまでお布施をするのか?と疑問を持たれる方も多いかもしれません。昔からの伝統や習わしに疑問を持つ方も多いのです。
お布施を渡すのはマナー?
お布施を渡すことは、仏教における伝統的なマナーとして行われています。
墓じまいの際、先祖の魂を大切に供養するために、僧侶が行う「閉眼供養」という儀式があります。この儀式の御礼として、僧侶にお布施を渡すのが一般的なマナーとなっています。
お布施のポイント
- 僧侶が行う閉眼供養は、先祖の魂を大切に供養する儀式です。
- この儀式のお礼として、僧侶にお布施を渡すのがマナーです。
- 閉眼供養をしないと、お墓の撤去や新しい場所での供養が難しくなることがあります。
- きちんとした供養を行うため、僧侶に依頼することが大切です。
閉眼供養は墓じまいの大切な儀式。その御礼としてのお布施は、感謝の気持ちを示すマナーとして欠かせないものです。
ずっと同じ場所にあった墓の中にあった遺骨を移動させるわけですから、何か祟りがあると感じる方も少なくありません。そんな不吉な状況にならないように、僧侶に儀式をしてもらいます。お布施はそのためでもあります。
お布施に法的な根拠はあるの?
お布施には法的な義務はありませんが、宗教的な背景や伝統に基づいて行われています。
お布施は、法的な義務や対価としての要素はなく、心からの感謝の気持ちを示すためのものです。そのため、お寺側が特定の金額を指定することは基本的にありません。
お布施に関するポイント
- お布施は法的な根拠がなく、対価としての性質はありません。
- お寺側が金額を指定することは基本的にない。
- 墓じまいの際の状況によって、相場の金額をお渡しするのが難しい場合もある。
- 金額について心配な場合は、親戚や寺院側に事前に相談すると良い。
- できる範囲でのお布施で十分と考えられる。
お布施は心からの感謝の気持ちを示すもので、法的な義務はない。しかし、適切な手続きと感謝の気持ちを持って行うことが大切です。
できる範囲で良いとされていますが、一般的な費用というものは存在します。少なすぎるからと言って、寺院から白い目で見られることはありませんが、一般的な費用を支払っておいた方が、この先の便宜を図ってくれる関係上、良いと思われます。
墓じまいのお布施の相場と費用

墓じまいをする際、お布施の相場やその他の費用について気になる方も多いでしょう。このセクションでは、お布施の相場や、それ以外にかかる費用について詳しく解説します。
菩提寺へのお布施の相場
墓じまいをする際、菩提寺へのお布施はどれくらいの金額が相場なのでしょうか。
菩提寺へのお布施の相場は、一般的に3〜10万円程度とされています。しかし、地域や寺院の方針、長年の付き合いの深さなどによって、この金額は変動することがあります。
菩提寺へのお布施のポイント
- 一般的な相場は3〜10万円。
- 地域や寺院の方針によって相場は変わることがある。
- 長年の付き合いがある場合、10万円以上をお渡しすることも。
- 個人的に僧侶に依頼する場合も、この相場が参考になる。
- 事前に家族や近所の人に相場を確認するのがおすすめ。
菩提寺へのお布施は3〜10万円が相場ですが、具体的な金額は地域や寺院の方針、関係の深さによって異なるので、事前の確認が大切です。
寺院に直接「いくらですか?」と聞くのは、空気を読まない人と思われがちです。同じレベルの寺院の檀家の方で、お布施を払っている場合、墓じまいの時のお布施の金額はおよそそこから2〜3倍と言われています。
オンラインでの依頼の相場
最近では、オンラインで墓じまいの手続きを依頼することも増えてきました。
インターネットを利用して僧侶を手配する場合、お布施の相場は3〜5万円程度となっています。特に、公営墓地や民間墓地にお墓がある場合や、菩提寺が特定できない場合には、この方法が選ばれることが多いです。
ネットでのお布施のポイント
- お布施の相場は3〜5万円。
- 公営墓地や民間墓地の場合、菩提寺がないことも。
- インターネットで僧侶を手配することが可能。
- 料金があらかじめ提示されている場合もある。
- 料金については、事前に確認することが大切。
ネットを利用して僧侶を依頼する場合、お布施の相場は3〜5万円ですが、事前に料金を確認しておくことが大切です。寺院を持っていない僧侶もオンライン上には多数存在しています。寺院の維持費がかからないので、安価になります。
お布施以外にかかる費用
墓じまいをする際、お布施だけでなく、その他の費用も考慮する必要があります。
墓じまいを行う際、閉眼供養のお布施以外にもいくつかの費用が発生することがあります。これらの費用は、僧侶の移動や食事、寺院との関係性などによって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
墓じまいの際の追加費用
- お車代:僧侶が墓地まで出向く場合の交通費。相場は5千円〜1万円。
- 御膳料:墓じまいの後の会食で僧侶が参加しない場合の食事代。食事と同額を包む。
- 離檀料:寺院墓地の墓じまい時、寺院との関係を終了する際の感謝のお金。相場は5〜20万円。
- お布施とは別の封筒を用意して包むのが一般的。
墓じまいの際、お布施だけでなく、移動や食事、寺院との関係終了などで追加の費用が発生することがあるので、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
僧侶にかかる費用として、お布施以外にこのような費用がかかります。離断料も払っているのに上乗せでお布施も払う?と疑問に感じるかもしれませんが、別ののし袋を用意するようにしましょう。
お布施を渡すタイミング

墓じまいをする際、お布施をいつ渡すのが適切なのか、そのタイミングについて気になる方も多いでしょう。このセクションでは、供養前と供養後、それぞれのお布施の渡し方について詳しく解説します。
供養前に渡すべき?
墓じまいの際、供養前にお布施を渡すことが一般的です。
墓じまいの際のお布施は、供養が始まる前に僧侶に渡すのが一般的です。しかし、場所や状況によっては、お布施の渡し方を工夫する必要があります。
供養前のお布施の渡し方
- 挨拶とともに:僧侶が到着したとき、「本日はよろしくお願いいたします」と言いながらお布施を渡す。
- 控室の確認:僧侶の控室がある場合、供養前にお布施を渡すのが良い。
- 紛失のリスク:控室がない、または鍵がかかっていない場合、お布施を紛失する恐れがあるので、供養前の渡しは避ける。
墓じまいの際のお布施は、供養前に僧侶に渡すのが基本ですが、場所や状況によっては注意が必要です。安心してお布施を渡せるよう、事前に状況を確認しましょう。
通常は後払いですが、しっかりと式を行ってもらいたい場合、気持ちよく行ってもらうために先に渡すというのも方法の一つです。
供養後はどうする?
供養が終わった後も、改めてお布施を渡すことがあるかもしれません。供養が終わった後にお布施を渡す場合の注意点とマナーについて説明します。
供養後のお布施の渡し方
- 供養後の対応:供養前にお布施を渡せなかった場合、供養が終わった後でも大丈夫です。
- 僧侶の帰宅前に:供養が終わった後、僧侶が帰る前にお布施を渡すことを忘れないようにしましょう。
供養が終わった後でも、お布施を渡すことは可能です。しかし、僧侶が帰る前に渡すことを心がけ、感謝の気持ちを伝えることが大切です。
僧侶の紛失を考えると、後に渡した方が安全と考えられるのであれば後で渡すのが良いでしょう。儀式の最中に盗難はあまり考えにくいですが、万一紛失となった場合は、誰も責任が取れないので、帰り際に渡すというのは方法の一つです。
お布施のマナーと渡し方

墓じまいの際、お布施を渡すことは大切なマナーの一つです。しかし、どのようなのし袋を使うべきか、表書きや裏書きの正しい書き方、そしてお布施の正しい包み方について知っておくことは重要です。このセクションでは、それらのマナーと具体的な渡し方について、わかりやすく解説します。
どんなのし袋を使うべき?
お布施を渡す際ののし袋選びは、心遣いの一つとして大切です。
墓じまいの際にお布施を渡す袋の選び方について、適切なものから避けるべきものまで詳しく説明します。正しい袋を選ぶことで、故人や僧侶への敬意を示すことができます。
お布施の袋の選び方
- 基本の袋:白無地の封筒が最も無難です。
- 奉書紙の利用:より丁寧に包む場合、和紙の奉書紙を使うことができます。
- 避けるべき封筒:郵便番号欄があるものや、二重の袋は避けるようにしましょう。
- 水引の選び方:地域や状況によって、水引の色や種類を変えることがあります。関西では黄白や双銀、喪中は黒白が一般的です。
- 確認の大切さ:不安な場合は、親戚やお寺の世話役に相談して確認することがおすすめです。
墓じまいの際のお布施の袋選びは、故人や僧侶への敬意を示す大切なポイントです。基本は白無地の封筒を選ぶことで、心を込めて感謝の気持ちを伝えることができます。
表書きの正しい書き方
お布施ののし袋の表書きは、渡す相手や目的に応じて変わります。
墓じまいの際にお布施を渡すときの表書きの書き方について、正しい方法をご紹介します。正確な表書きで、故人や僧侶への敬意を示すことができます。
お布施の表書きのポイント
- 筆の選び方:毛筆や筆ペンを使って書くと、格式が出ます。
- 墨の濃さ:薄い墨よりも濃い墨で書くのがおすすめです。
- 表書きの内容:上側中央に「御布施」と書き、下側中央に自分の名前を記載します。名前は名字だけで大丈夫です。
- 他の費用の表書き:車代や御膳料を包む場合は、それぞれ「御車代」、「御膳料」と書くことを忘れないようにしましょう。
墓じまいの際のお布施の表書きは、故人や僧侶への感謝の気持ちを伝える大切な手続きです。正しい書き方を心がけて、心を込めてお布施を渡すことが大切です。
裏側・中袋の書き方のポイント
のし袋の裏側や中袋の書き方も、マナーとして知っておくべきポイントがあります。
墓じまいの際、外側が包みの形をしている多当折りタイプのお布施の場合、中袋がついています。この中袋には、自分の情報や金額を正しく記載することが大切です。
中袋の書き方のポイント
- 金額の記載場所:
- 表側中央に「金○○圓也」と書きます。
- 金額部分は漢数字で表記。
- 裏側の記載情報:
- 左下に、住所、名前、電話番号を書きます。
- 漢数字の使用:
- 金額の部分は封筒の裏側と同じく、漢数字で書く。
多当折りタイプのお布施の場合、中袋に自分の情報や金額を正確に記載することで、お布施の意味が深まり、受け取り手にも感謝の気持ちが伝わります。
また、複数の儀式を回る場合に、誰から受け取ったものなのか?わからなくことを避けるために、ご自身の情報をしっかりと記載することが大切です。
お布施の正しい包み方
お布施を渡す際の包み方も、心遣いの一部として大切です。
墓じまいの際のお布施を包むとき、封筒の裏側や中袋にも重要な情報を書く必要があります。正確に記載することで、お布施の受け取り手が内容を確認しやすくなります。
お布施の裏側・中袋の書き方のポイント
- 封筒の種類による書き方:
- 中袋がない場合:封筒の裏側に情報を記載
- 中袋がある場合:中袋に情報を記載
- 記載する情報:
- 左下に、右から順に住所、氏名、電話番号、金額を書きます。
- 金額の書き方:
- 「金○○圓也」という形式で記載
- 金額部分は漢数字で書く
- 漢数字の参考:
- 5千円:「金伍阡圓也」
- 3万円:「金参萬圓也」
- 一→壱、二→弐、三→参、五→伍、十→壱拾、千→阡、万→萬
墓じまいの際のお布施を正しく包むためには、封筒の裏側や中袋にも注意深く情報を記載することが大切です。正確な情報を伝えることで、お布施の意味が深まります。
お布施を渡すことに対して、渡す方は初めてでも、受け取る僧侶側からするとどのような形式が正しいものなのか?わかっています。正しい書き方をしないとすぐにわかってしまうので注意が必要です。
ただ、そこまで気にする僧侶の方も少ないので、しっかりと感謝の気持ちが伝われば問題ないでしょう。
Auto Amazon Links: プロダクトが見つかりません。
まとめ:墓じまいのお布施を渡すタイミングと費用
墓じまいを進める際、お布施のタイミングや費用についての疑問や不安を感じる方も多いでしょう。このセクションでは、墓じまいの際のお布施に関する基本的な知識とマナーを、わかりやすくまとめてご紹介しました。
墓じまいの際、お布施をいつ渡すのが適切なのか、そのタイミングが気になる方もいるでしょう。
供養前にお布施を渡すのが一般的ですが、地域や宗派によっては供養後に渡すこともあります。お布施は感謝や尊敬の意を示すためのものであり、供養の際に僧侶への感謝の気持ちを表現するために渡されることが多いです。
墓じまいの際のお布施の費用や相場についても、正確な情報を知りたいと思う方は多いでしょう。
お布施の相場は地域や宗派、寺院によって異なりますが、一般的には数万円から十数万円程度とされています。お布施の金額は故人や家族の感謝の気持ちを示すものであり、適切な金額を渡すことで、故人への敬意を示すことができます。
お布施以外にも費用の面で負担があり、特に離断料は大きな割合を占めます。できるだけ少なく済ませたいという気持ちから、墓じまいの儀式がおろそかになり、親戚から非難を浴びたり、後悔したりしないようにすることが大切でしょう。

私は墓の管理と墓じまいの専門家であり、10年を超える長きにわたり、墓の管理に困っている多くの家族に墓じまいの提案とサポートを行ってきました。
特に公営の墓地での一定期間の放置による墓の撤去や、墓の管理の困難さ、維持費の問題など、多くの家族が墓じまいを検討する理由はさまざまです。墓じまいの過程で必要となる墓地の管理者との相談や新しい供養の場所の選定など、これまでの経験を踏まえ、サポートするという視点で、墓の管理に困っている人を助けることができたらと感じています。